従業員の出勤状況や労働時間を記録する「勤怠データ」。
うまく活用すれば、業務のムダや人員配置の偏りを見つけたり、コンプライアンス対応にも大きく役立ちます。
近年では、勤怠管理システムを使ってデータを蓄積し、情報を「見える化」し、改善アクションにつなげることが重視されています。
本記事では、勤怠データの基本的な内容から、具体的な分析指標や方法、そして実際の業務改善への活かし方まで、体系的にまとめました。
1.勤怠データとは?取得できる主な情報
勤怠管理システムでは、従業員の働き方に関するさまざまなデータを自動的に記録・蓄積できます。
これらの「勤怠データ」は、単なる出退勤の記録にとどまりません。
労働時間の把握や業務改善、法令遵守の観点からも非常に重要な役割を果たします。
勤怠管理で取得できる代表的なデータを以下のように分類しました。
・出勤・退勤時刻
・実労働時間・所定労働時間
・残業時間・深夜労働時間
・有給休暇の取得状況
・打刻ミスや勤怠修正の履歴
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)出勤・退勤時刻
勤怠データの中でも最も基本的なのが「出勤・退勤時刻」です。
従業員がいつ出勤し、いつ退勤したかを正確に記録することで、労働時間や遅刻・早退の有無が明確になります。
定時が9:00〜18:00の職場で、8:50に出勤し17:55に退勤したというデータが残れば、その日の労働状況が一目で把握できます。
日々の勤務状況を正しく記録するうえで欠かせない情報です。
(2)実労働時間・所定労働時間
「実労働時間」とは、実際に働いた時間のことで、「所定労働時間」との差異が勤怠の評価指標になります。
この2つのデータを照らし合わせることで、時間外労働の発生状況や業務の過不足が見えてきます。
所定8時間に対して実働6時間の日が続けば、生産性やシフトの見直しが必要かもしれません。
勤務の適正化に向けた分析には不可欠な指標といえます。
(3)残業時間・深夜労働時間
残業や深夜勤務に関するデータは、長時間労働の有無や、割増賃金の正確な支給に直結します。
特に法定労働時間を超えた分や22時以降の深夜時間は、企業の労務管理上も重要なチェックポイントです。
ある部署だけ残業時間が突出していれば、業務配分や人員体制に課題がある可能性が考えられます。
働きすぎの抑制と労働環境の改善に役立つ情報です。
また、最近は時間帯で時給を変動させている企業も多くあるため、「時間帯ごとの労働時間」のデータも重要です。
どの時間帯にどれだけ働いたかを把握することで、正確な給与計算を可能にします。
(4)有給休暇の取得状況
有給休暇の取得日数や取得率も、勤怠データから把握できます。
取得状況を可視化することで、休暇が偏っていないか、制度が適切に機能しているかを確認できます。
有休の消化率が低い部署があれば、業務量の偏りや管理職の運用方針に問題があるかもしれません。
法令順守と職場の働きやすさを両立させるためにも注視すべき項目です。
(5)打刻ミスや勤怠修正の履歴
打刻忘れや修正回数の多さも、勤怠データから抽出できる情報のひとつです。
頻繁に修正が発生している場合は、運用フローやシステムの使い方に課題がある可能性があります。
スマホ打刻の精度が悪く、同じ人が何度も修正申請をしていれば、仕組みそのものの見直しが必要です。
信頼性の高い勤怠管理を実現するには、こうしたミスの分析も欠かせません。
2.勤怠データを分析する目的とは

勤怠データは、単なる出退勤の記録にとどまらず、企業運営にとって重要な「経営資源」として活用できます。
働き方の多様化やコンプライアンス強化が求められる今、勤怠データを分析する目的は、単なる集計作業ではなく「改善・改革」に直結するものとなっています。
適切に分析することで、現場の実態把握や業務効率の向上、さらには人材マネジメントまで幅広く活かすことが可能です。
この章では、勤怠データを分析する代表的な目的を5つに整理しました。
・労働時間の適正管理
・生産性の可視化と改善
・人員配置の最適化
・働き方改革・制度設計の判断材料にする
・従業員のコンディション把握と離職防止
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)労働時間の適正管理
勤怠データを分析する主な目的のひとつは、従業員の労働時間を正確に把握し、適正に管理すること。
過重労働やサービス残業を防ぎ、労働基準法を遵守するうえでも、データの可視化は欠かせません。
部署ごとの平均残業時間を比較することで、業務過多になっているチームを早期に発見できます。
コンプライアンス対応だけでなく、働きやすい職場づくりにもつながる取り組みです。
(2)生産性の可視化と改善
勤怠データを分析すると、「何時間働いたか」だけでなく、「その時間がどれだけ有効だったか」も見えてきます。
労働時間に対する成果や業績と照らし合わせることで、無駄の多い時間帯を特定できます。
同じ8時間勤務でも、営業成績やタスク消化量に大きな差があれば、業務改善のヒントが得られるはずです。
限られたリソースを有効に使うためにも、定量的な分析が欠かせません。
(3)人員配置の最適化
日別・時間帯別・部門別に勤怠データを分析することで、人員が不足している時間や過剰なシフトを把握できます。
この情報をもとに、現場の負荷を平準化したり、必要に応じた人員増強や削減の判断が可能になります。
ある曜日の午後だけ退勤者が集中しているなら、その時間帯に残業が偏っている可能性があるでしょう。
人件費を無駄なく使うためにも、データに基づいた配置調整が重要です。
(4)働き方改革・制度設計の判断材料にする
勤怠データの分析は、企業の働き方改革や制度設計の根拠にもなります。
柔軟な勤務制度の導入や、フレックスタイムの有効性を検証するうえで、定量的な裏付けが必要です。
時差出勤制度を導入してから出勤集中時間が分散されたというデータがあれば、施策の効果が示せます。
現場の実態に即した改革を行うには、実測データの活用が不可欠です。
(5)従業員のコンディション把握と離職防止
勤怠データは、従業員の心身のコンディションやモチベーションを見極める材料にもなります。
極端な残業や連勤、有給の未取得が続いていれば、疲労やストレスが蓄積している可能性があります。
月後半に欠勤や遅刻が集中する人がいれば、早めのフォローが必要になるかもしれません。
離職リスクの早期発見にも役立つ視点です。
3.勤怠データから得られる具体的な指標
勤怠データを分析するうえで、重要になるのが「何を指標として見るか」という視点です。
単に労働時間を集計するだけでは、現場の課題や改善点を浮き彫りにすることはできません。
出勤状況や休暇取得、残業の偏りなどを数値化することで、客観的かつ具体的な判断が可能になります。
また、これらの指標は部署単位・時期別に比較することで、さらに深い分析にもつながります。
この章では、勤怠データから導き出せる代表的な指標を5つ紹介します。
・出勤率・欠勤率
・残業時間・残業率
・有給休暇取得率
・遅刻・早退の回数
・打刻ミス・修正申請の件数
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)出勤率・欠勤率
出勤率と欠勤率は、勤怠データの中でも基本かつ重要な指標です。
従業員がどの程度安定して勤務しているかを示す数値で、組織の健康状態を把握する第一歩となります。
ある部署だけ欠勤率が高い場合、業務負荷や職場環境に問題がある可能性があります。
出勤状況の可視化は、離職やモチベーション低下の予兆を察知する手がかりにもなります。
(2)残業時間・残業率
残業に関する指標は、過重労働の有無や業務配分の偏りを把握するために欠かせません。
残業時間の推移を追うことで、繁忙期や人手不足のタイミングを可視化できます。
特定の時期に残業が集中していれば、スケジュール管理やシフト体制の見直しが求められるかもしれません。
従業員の負担軽減や法令順守にもつながる大切なデータです。
(3)有給休暇取得率
有休取得率は、従業員が適切に休めているかどうかを示す重要な指標です。
制度として整備されていても、実際に取得されていなければ意味がありません。
年5日の取得義務があるにもかかわらず未達の社員が多ければ、企業としてリスクを抱えていることになります。
働きやすい職場づくりの基盤として、定期的に確認すべき数値です。
(4)遅刻・早退の回数
遅刻や早退は、勤怠の乱れや体調・メンタル面の不調を示すサインになることがあります。
データとして蓄積し、一定期間で傾向を確認することで、従業員のコンディションや職場課題の早期発見につながります。
特定の曜日や時間帯に偏って発生している場合、勤務体系や通勤事情に課題があるかもしれません。
小さな変化の蓄積が、将来的なトラブルの予防になります。
(5)打刻ミス・修正申請の件数
打刻ミスや修正申請が多い場合、運用ルールやシステム自体に課題が潜んでいる可能性があります。
放置すると、正確な勤怠把握ができず、給与計算や労務管理にも影響を及ぼします。
モバイル打刻で位置情報がうまく取得できないといったトラブルが頻発していれば、機器や通信環境の見直しが必要です。
正確性と信頼性の高い勤怠運用のために、見逃せない指標といえるでしょう。
4.勤怠データの分析方法

勤怠データを取得しても、それを活用できなければ意味がありません。
データは集めるだけでなく、整理し、比較し、現場の課題を浮き彫りにすることではじめて「使える情報」になります。
分析の方法は企業規模や目的に応じてさまざまですが、ツールの選び方ひとつで業務の効率や成果が大きく変わります。
この章では、勤怠データを分析する代表的な手法を3つ紹介します。
・Excelやスプレッドシートでの集計
・BIツールやダッシュボードの活用
・勤怠管理システムのレポート機能
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)Excelやスプレッドシートでの集計
もっとも手軽に始められる分析方法が、ExcelやGoogleスプレッドシートを使った集計です。
シンプルな操作でデータのフィルタリングやグラフ化ができ、誰でも扱えるのが魅力です。
「部署別の残業時間」や「月別の有休取得率」といったデータを関数で集計すれば、傾向の可視化が簡単に行えます。
初期費用をかけずに分析を始めたい企業には、有効な手段といえるでしょう。
(2)BIツールやダッシュボードの活用
より高度な分析や、リアルタイムでの可視化を求める場合には、BIツールの導入が効果的です。
部署ごとの傾向比較や異常値の検知を自動で行えるため、データドリブンな意思決定が可能になります。
PowerBIやLookerStudioなどを使えば、勤怠情報をグラフ化し、経営層が一目で状況を把握できる仕組みを構築できます。
戦略的に勤怠データを活用したい企業には、強力な武器となります。
ただし活用するには専門的な知識が必要です。
(3)勤怠管理システムのレポート機能
近年の勤怠管理システムには、標準でレポート機能が搭載されていることが多く、集計から分析までワンストップで対応できます。
出勤率・残業時間・有給取得率などの指標が自動で算出され、手作業による集計ミスのリスクも軽減されます。
「月別の遅刻回数」や「残業の多いスタッフランキング」など、定型レポートを出力するだけで状況を把握できるケースもあります。
データ活用の効率化と精度向上を目指すなら、システム内の分析機能を活用しない手はありません。
5.分析結果をどう活かす?業務改善につなげる視点
勤怠データを集計・分析するだけでは、業務改善にはつながりません。
重要なのは、そこから得られた気づきをどう現場の運用や制度に反映させていくかという実行フェーズです。
データに基づく判断を行うことで、感覚や慣習に頼らない、合理的で納得感のある改善策を打ち出せるようになります。
この章では、分析結果を活用して改善すべき代表的な視点を4つご紹介します。
・シフト見直しや人員配置の最適化
・長時間労働の是正
・休暇制度の見直しと促進
・従業員のモチベーション管理
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)シフト見直しや人員配置の最適化
勤怠データから出勤率や業務負荷を把握することで、シフトや人員配置のムラを是正できます。
時間帯別や曜日別の傾向を分析すれば、業務量と人手のバランスを客観的に判断できます。
午後に残業が集中している場合、早番と遅番のバランスを見直すことで過重労働の抑制が可能になります。
限られた人員で成果を最大化するには、データに基づく配置調整が欠かせません。
(2)長時間労働の是正
残業時間や連勤日数の分析により、過度な労働が常態化している部署や個人を特定できます。
こうした負担の偏りは、従業員の健康リスクや離職にも直結する重要な課題です。
残業時間が月に80時間を超えている社員が複数いる場合、業務分担や採用の見直しが急務といえるでしょう。
働き方改革を進めるうえでも、長時間労働の可視化と対応が求められます。
(3)休暇制度の見直しと促進
有給休暇の取得率や取得傾向を分析することで、制度が実際に機能しているかを検証できます。
部署ごとの差や時期ごとの偏りを把握することで、取得しやすい環境づくりへの具体的な施策につなげられます。
年末や繁忙期に取得率が著しく低下している場合は、交代要員の確保や申請手順の見直しが必要かもしれません。
制度を「あるだけ」にせず、活用される仕組みへと進化させることが重要です。
(4)従業員のモチベーション管理
勤怠データには、従業員の状態や職場への満足度を間接的に示す情報が含まれています。
遅刻・早退・欠勤の頻度、休暇取得の有無、残業の偏りなどから、モチベーションの低下や疲弊の兆しが読み取れることも。
以前は皆勤だった社員が突然欠勤を繰り返すようになった場合、フォローが必要になる可能性があります。
組織の安定運営のためにも、定期的なモニタリングが有効です。
勤怠データの分析機能も充実!「R-Kintai」

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。
徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。
打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。

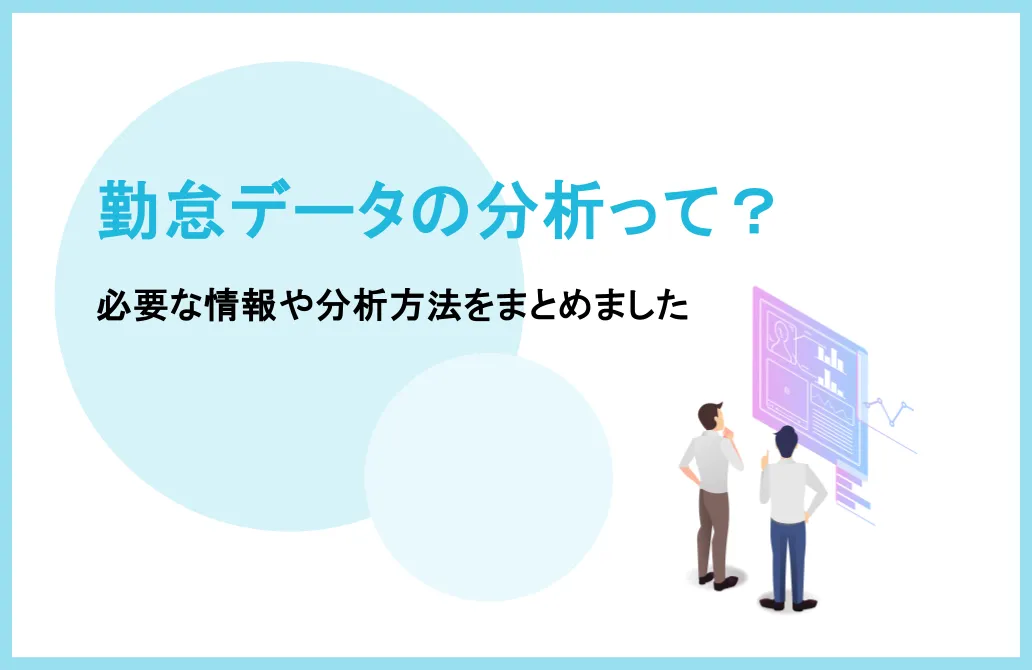
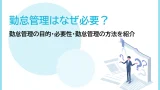


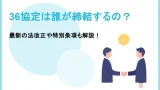


人気記事