企業の労務管理において、勤怠管理は欠かせない業務のひとつです。
しかし、従来の手作業による管理では、打刻ミスや申請の遅れ、労働時間の不透明さなど、多くの課題が発生しがちです。
こうした問題を解決する手段として、多くの企業が勤怠システムを導入しています。
勤怠システムを活用すれば、出退勤の記録が自動化され、業務負担の軽減や精度向上が期待できます。
法令遵守やリモートワークの対応など、現代の働き方に適した管理が可能になるでしょう。
この記事では、勤怠システムの主な機能や導入のメリット、必要性について解説します。
勤怠管理の効率化を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1. 勤怠システムの主な機能とは
勤怠システムには、単なる出退勤の記録だけでなく、労働時間の適正管理や業務効率の向上を支援するさまざまな機能が備わっています。
従業員がスムーズに勤務を報告できる仕組みを整え、管理者はリアルタイムで労働状況を把握しやすくなるでしょう。
また、給与計算システムやシフト管理システムとの連携により、より精度の高い勤怠管理が可能になります。
ここでは、勤怠システムの主な機能について解説します。
・出勤・退勤の打刻
・残業・休暇の申請ワークフロー
・勤怠状況の把握
・管理者向けの帳票出力・分析
・テレワーク対応機能
・シフト管理や給与計算システムとの連携
それぞれ詳しく見ていきましょう。
(1) 出勤・退勤の打刻
出勤や退勤の打刻は、勤怠管理の基本となる機能です。
従業員が正確な勤務時間を記録できるよう、ICカード、スマートフォン、PC、生体認証など複数の方法が用意されています。
不正打刻を防ぎながら利便性を高めることが可能です。
また、リアルタイムでの打刻データ取得により、管理者は勤務状況を即座に把握できるでしょう。
(2) 残業・休暇の申請ワークフロー
残業や休暇の申請は、ワークフロー機能を活用することでスムーズに処理できます。
従業員がシステム上で申請し、上長がオンラインで承認できるため、紙を使う手間が省けます。
また、承認フローを自動化することで、申請の抜け漏れを防ぐことができるでしょう。
適正な労働時間管理にもつながり、働き方改革の推進にも貢献します。
(3) 勤怠状況の把握
管理者は、従業員の勤怠状況をリアルタイムで確認できます。
出勤状況や遅刻・早退、休暇の取得状況を一目で把握できるため、迅速な対応が可能です。
長時間労働や過重労働の兆候を早期に発見し、労務リスクを軽減できます。
さらに、分析機能を活用すれば、業務効率の改善にもつながります。
(4) 管理者向けの帳票出力・分析
勤怠データは、帳票として出力し、給与計算や労務管理に活用できます。
労働時間や残業時間の集計を自動化すれば、業務負担を大幅に軽減できるでしょう。
また、蓄積されたデータを分析することで、勤務状況の改善点が明確になります。
組織全体の生産性向上につながるはずです。
(5) テレワーク対応機能
リモートワークが普及する中、テレワーク対応の勤怠管理は欠かせません。
GPS打刻やIPアドレス制限を活用すれば、不正打刻を防ぎ、適正な管理が可能になります。
管理者が離れた場所でも勤務実態を把握しやすくなるでしょう。。
(6) シフト管理や給与計算システムとの連携
勤怠システムは、シフト管理や給与計算システムと連携させることで、さらなる業務効率化が期待できます。
シフトデータを自動で取り込み、実績と比較することで、労働時間のズレや過不足をすぐに確認できます。
また、給与計算システムと連携すれば、勤怠データをそのまま給与計算に反映できるため、手作業によるミスも減るでしょう。
統合管理により、企業全体の労務管理がスムーズになります。
2. なぜ勤怠システムが必要なのか
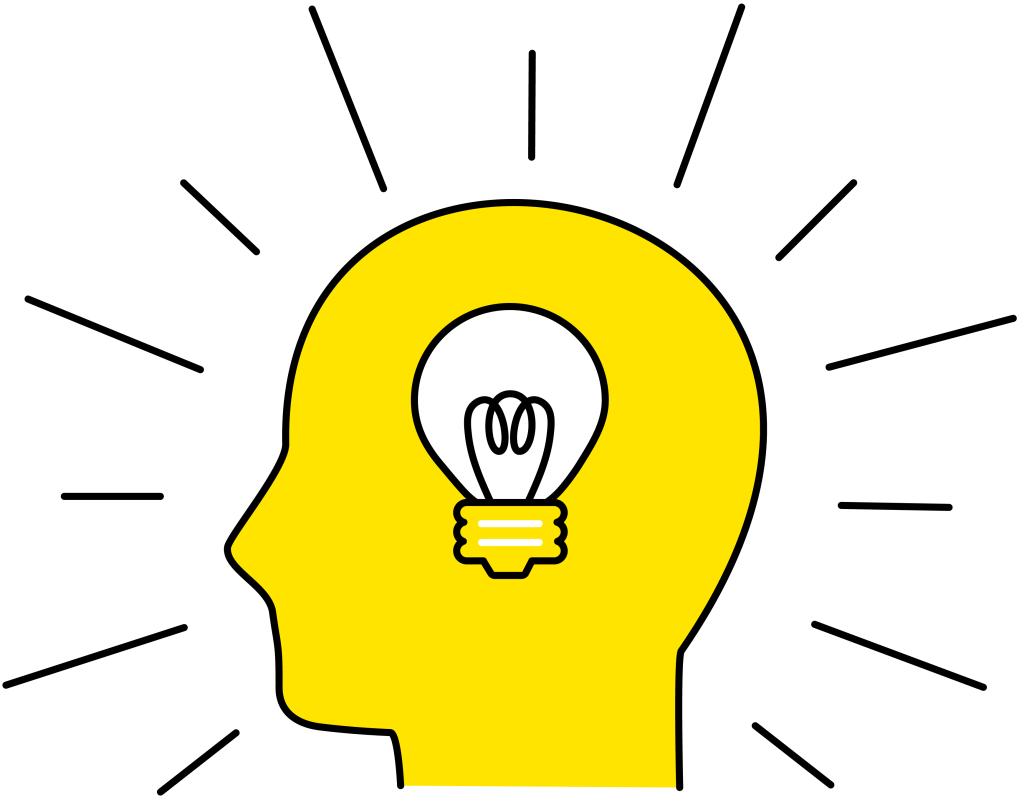
企業における勤怠管理は、労働時間の適正な管理や給与計算の正確性向上に直結する重要な業務です。
しかし、手作業での管理は負担が大きく、ミスやトラブルが発生しやすくなります。
勤怠システムを導入すれば、業務の効率化や法令遵守の強化が可能になり、従業員の働きやすさにもつながるでしょう。
ここでは、勤怠システムの導入が必要とされる理由について解説します。
・労務管理の負担軽減(担当者の業務削減)
・労働基準法違反のリスク回避(適切な労働時間管理)
・給与計算の正確性向上(未払い残業の防止)
・従業員満足度の向上(透明性のある勤怠管理)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
(1) 労務管理の負担軽減(担当者の業務削減)
勤怠管理を手作業で行うと、データの集計や確認に多くの時間がかかります。
特に、紙のタイムカードやエクセル管理では、入力ミスや集計漏れが発生しやすく、担当者の負担が大きくなりがちです。
勤怠システムなら、出退勤のデータが自動で記録・集計され、業務の手間を大幅に削減できます。
リアルタイムで勤怠状況を確認できるので、修正対応や問い合わせ業務の負担も軽減されるでしょう。
(2) 労働基準法違反のリスク回避(適切な労働時間管理)
労働基準法では、適正な労働時間の管理が求められています。
しかし、手作業では違反リスクをゼロにするのは困難です。
長時間労働の把握の遅れ、未払い残業の発生などは、企業の信頼を損ない、行政指導や罰則を受ける可能性もあります。
勤怠システムなら、残業時間や休憩時間を自動で記録し、違反の兆候をリアルタイムで検知できます。
法令を遵守しながら、適正な労働環境を維持しやすくなるでしょう。
(3) 給与計算の正確性向上(未払い残業の防止)
給与計算の精度は、従業員の信頼を維持するうえで非常に重要です。
手作業での勤怠データ管理では、計算ミスや入力漏れが発生しやすく、未払い残業や誤った給与支給につながるリスクがあります。
勤怠システムを活用すれば、打刻データが自動集計され、給与計算システムとの連携で正確な支給が可能に。
ミスを防ぐだけでなく、計算にかかる時間も大幅に短縮できるでしょう。
(4) 従業員満足度の向上(透明性のある勤怠管理)
不透明な勤怠管理は、従業員の不満の原因になりやすいものです。
「残業時間が正しく計上されていない」「休暇の申請が適切に処理されない」などの問題が発生すると、信頼関係が損なわれる可能性があります。
勤怠システムを導入すれば、従業員が自分の労働時間や休暇の取得状況をリアルタイムで確認できるため、透明性が向上します。
また、申請や承認がスムーズに行われることで、労働環境の改善にもつながるでしょう。
3. 勤怠システム導入のメリットとは?

勤怠システムを導入することで、企業の労務管理が大きく改善されます。
手作業での管理ではミスが発生しやすく、従業員の負担も増えてしまいますが、システム化すればそのリスクを最小限に抑えられるでしょう。
ここでは、勤怠システムの導入によって得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。
・手作業によるミスの削減(自動集計・エラー防止)
・業務効率化と生産性向上(集計や申請の手間を削減)
・労務管理の透明化(不正打刻防止・リアルタイム把握)
・法令遵守のサポート(労働時間の適正管理)
・多様な働き方に対応(リモートワーク・フレックスタイム)
以下、それぞれ見ていきましょう。
(1) 手作業によるミスの削減(自動集計・エラー防止)
勤怠管理を手作業で行うと、集計ミスや入力ミスが発生しやすくなります。
特に、エクセルや紙のタイムカードを使用している場合、計算のずれや記録漏れが問題となることが少なくありません。
勤怠システムを導入すれば、打刻データが自動で集計されるため、人為的なミスを防ぐことができます。
また、エラー検出機能があるシステムなら、不正打刻や異常な勤務時間を即座に把握できるでしょう。
(2) 業務効率化と生産性向上(集計や申請の手間を削減)
勤怠データの集計や残業・休暇の申請処理は、手作業では大きな負担になります。
毎月の給与計算時には、時間をかけてデータを整理し、確認する必要があるため、業務の効率を下げてしまうでしょう。
勤怠システムを活用すれば、打刻データの集計が自動化され、申請・承認のフローもスムーズに進みます。
管理者の負担が軽減されるだけでなく、従業員も迅速に手続きを進めることが可能になります。
(3) 労務管理の透明化(不正打刻防止・リアルタイム把握)
労務管理の透明性を確保することは、企業の信頼性向上につながります。
従来の紙ベースやエクセル管理では、勤務時間の改ざんや不正打刻のリスクがあり、管理が煩雑になりがちです。
勤怠システムを導入すれば、ICカードや生体認証を活用した正確な打刻が可能になり、不正を防ぐことができます。
さらに、リアルタイムで勤務状況を確認できるため、適切な労務管理が実現しやすくなるでしょう。
(4) 法令遵守のサポート(労働時間の適正管理)
労働基準法では、適正な労働時間管理が求められており、違反すると企業が行政指導や罰則を受ける可能性があります。
長時間労働の管理が不十分な場合、従業員の健康リスクや未払い残業の問題が発生することも考えられるでしょう。
勤怠システムには、36協定の上限を超える残業の警告機能や、休憩時間の自動管理機能が備わっています。
企業は法令を遵守しながら、適正な労働環境を維持しやすくなります。
(5) 多様な働き方に対応(リモートワーク・フレックスタイム)
働き方の多様化が進む中、企業にはフレキシブルな勤務管理が求められています。
従来のオフィス勤務だけでなく、リモートワークやフレックスタイム制度を導入する企業も増えてきました。
勤怠システムを導入すれば、GPS打刻やシフト管理機能を活用し、場所や時間に縛られない勤務管理が可能になります。
従業員は柔軟に働くことができ、企業側も適切な労働時間の把握ができるようになるでしょう。
4. 勤怠システムの導入手順

勤怠システムを導入する際には、単にシステムを選ぶだけではなく、企業の実態に合った運用フローを整えることが重要です。
現状の課題を把握し、適切なシステムを選定したうえで、スムーズに導入・運用できるよう準備を進める必要があります。
導入後の教育や継続的な改善を行うことで、より効果的な勤怠管理を実現できるでしょう。
勤怠システムを導入する際の具体的なステップを解説します。
(1)現状の勤怠管理の課題を洗い出す
(2)勤怠システムを絞り込む
(3)無料トライアルやデモを活用して比較検討
(4)社内ルールの整備と導入準備
(5)導入後の運用と社員への教育
(6)継続的な改善・カスタマイズ
以下、それぞれについてまとめました。
(1) 現状の勤怠管理の課題を洗い出す
まずは、現在の勤怠管理の問題点を明確にすることが重要です。
手作業による集計ミス、長時間労働の管理不足、不正打刻のリスクなど、現場で発生している課題を洗い出しましょう。
具体的な課題を把握することで、勤怠システムに求める機能が明確になり、適切なシステムを選びやすくなります。
管理者だけでなく、実際にシステムを利用する従業員の意見も取り入れることが望ましいでしょう。
(2) 勤怠システムを絞り込む
課題を把握したら、要件に合った勤怠システムを比較・検討します。
システムには、クラウド型・オンプレミス型、シンプルなものから多機能なものまで、さまざまな種類があります。
企業の規模や運用方法に合ったシステムを選ぶことで、導入後の定着率が高まり、運用の負担も軽減できるでしょう。
導入コストやサポート体制も考慮し、最適なシステムを選定することが重要です。
(3) 無料トライアルやデモを活用して比較検討
勤怠システムの多くは、無料トライアルやデモを提供しているため、実際に使用感を試すことができます。
システムの操作性や画面の見やすさ、必要な機能が揃っているかを確認しながら比較検討しましょう。
また、導入後のサポート体制やカスタマイズの柔軟性についてもチェックしておくことで、運用時のトラブルを防ぐことができます。
実際の業務フローにどれだけ適合するかを見極めることが、成功のカギとなるでしょう。
(4) 社内ルールの整備と導入準備
システムの選定が完了したら、社内ルールを整備し、スムーズな導入準備を進めます。
勤怠システムの運用ルールや、シフト申請・残業申請の手順を明確にし、全従業員に周知することが必要です。
従業員の混乱を防ぐため、移行期間を設けて新旧システムを並行運用するのも効果的です。
スムーズな移行のためには、現場の意見を取り入れた柔軟な対応が求められます。
(5) 導入後の運用と社員への教育
システムを導入しただけでは、効果を最大限に発揮できません。
従業員が適切にシステムを活用できるよう、導入時の研修やマニュアルの整備が重要です。
管理者向けのトレーニングを実施し、勤怠データの確認・分析の方法を理解してもらうことで、より適正な運用が可能に。
導入直後の問い合わせやトラブルに備えて、フォロー体制を整備しておくとよいでしょう。
(6) 継続的な改善・カスタマイズ
勤怠システムは、導入後の運用を続ける中で、さらに最適化していくことが大切です。
システムの運用状況を定期的に確認し、従業員や管理者からのフィードバックをもとに改善を重ねましょう。
労働環境の変化や法改正に対応できるよう、システムのカスタマイズやアップデートを適宜行うことも必要です。
長期的に活用できる仕組みを構築することで、より効果的な勤怠管理が実現できるでしょう。
勤怠管理の機能が充実した「R-Kintai」

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。
徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。
打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。


人気記事