飲食業は、時間帯による繁閑差が大きく、パート・アルバイトのシフト勤務が主流です。
スタッフの入れ替わりも頻繁な業界であるため、日々の勤怠管理は複雑になりやすく、店長やマネージャーの大きな負担となっています。
適切な勤怠管理を行わないと、従業員の不満や法令違反のリスクに直結する可能性も。
本記事では、飲食業において勤怠管理がなぜ重要なのか、現場でよくある課題とその解決策について詳しく解説します。
1. なぜ飲食業において勤怠管理が重要なのか

飲食業は、労働環境が不規則になりやすく、勤怠管理の重要性が特に高い業界です。
労働状況が品質や運営の安定性に影響するため、正確かつ効率的な管理が欠かせません。
飲食業における勤怠管理の重要性を以下の観点から整理しました。
- 顧客サービスの質を守る労働環境の整備
- スタッフの定着率向上と人手不足対策
- 雇用形態ごとの管理負担の軽減
- 法令順守と労務リスクの回避
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1) 顧客サービスの質を守る労働環境の整備
飲食業は、ホールやキッチンなど現場スタッフの動きがサービス品質に直結します。
疲弊した状態や無理な労働環境下では、丁寧な接客を維持することが難しくなります。
繁忙時間帯に過少人員での営業が続けば、オーダーミスや料理提供の遅延が発生し、クレームにつながるリスクが高まるでしょう。
適正なシフト配置と正確な勤怠管理を行うことで、スタッフが安心して働ける環境を整える必要があります。
(2) スタッフの定着率向上と人手不足対策
飲食業界は人手不足が慢性的な課題となっており、離職防止が経営に直結します。
働きやすさを実感できる勤怠管理は、スタッフの定着率を高める有効な手段です。
「休憩が取れない」「シフトが不公平」といった不満が可視化されれば、早期に改善できます。
こうした問題が放置されると、不満が蓄積し、離職や不信感へとつながるでしょう。
勤怠データを通じて現場の課題を把握し、体制を整えることが重要です。
(3) 雇用形態ごとの管理負担の軽減
正社員・パート・アルバイト・短期スタッフなどの雇用形態が混在する飲食業界。
契約条件や労働時間、時給なども異なるため、勤怠管理は煩雑になりがちです。
手作業で個別対応をしていると、計算ミスや確認漏れが発生するリスクが高まります。
アルバイトの深夜手当や休日出勤の集計を誤ると、後のトラブルや給与再計算につながることも。
雇用形態ごとのルールに沿った管理ができれば、業務効率と精度の両立が図れます。
(4) 法令順守と労務リスクの回避
飲食業では、残業や深夜勤務が日常的に発生します。
労働基準法に則った勤怠管理が不可欠です。
記録の不備や法定労働時間の超過があれば、労働トラブルに発展する可能性もあります。
もし36協定の上限を超える労働が記録されていた場合、悪質だと判断されれば罰則の対象になりかねません。
リスク回避のためにも、打刻漏れや休憩時間の適正管理の徹底が求められます。
2. 飲食業でよくある勤怠管理の課題

現場では、日々のオペレーションに追われるなかで、勤怠管理にまで十分な手が回らないことが多くあります。
特に紙やエクセルでの勤怠管理は、手間やミスが発生しやすく、運営面にも悪影響が出てしまいます。
飲食業でよく見られる勤怠管理の課題を整理しました。
- 打刻漏れ・打刻ミスの頻発
- シフトと実労働時間の乖離
- 残業や休憩の管理が曖昧になる
- 勤怠集計作業が煩雑で時間がかかる
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1) 打刻漏れ・打刻ミスの頻発
飲食店では忙しい時間帯に出勤や退勤が重なることが多くあります。
打刻を忘れて業務に入るスタッフも珍しくありません。
たとえばランチのピーク時に「とりあえず厨房に入って手伝った」結果、タイムカードを押し忘れるといったケースがよく見られます。
こうした打刻漏れやミスは、修正対応が必要で、管理側の負担が増します。
打刻ミスの頻度が高い職場では、正確な労働時間の把握が困難に。
労働時間の申告に対する信頼性も損なわれかねません。
(2) シフトと実労働時間の乖離
作成されたシフトと実際の勤務時間がずれることも多くあります。
「20:00退勤予定だったが、ラストオーダーの対応で21:00まで残業」など、現場判断で勤務時間が変わることは日常茶飯事です。
その結果、タイムカードの記録とシフト表の整合性が取れず、給与計算や労働時間の管理に混乱を招きます。
ズレが常態化している場合、法定労働時間の超過に気づかないまま、労働基準法違反となるリスクも高まります。
(3) 残業や休憩の管理が曖昧になる
「混んでいたから休憩をとらなかった」「閉店後に片付けで残業した」など、現場の状況によって残業や休憩時間が柔軟に変更されることが多いのも飲食業の特徴です。
記録が曖昧なままだと、従業員とのトラブルや、未払い残業の問題に発展する可能性があります。
実際の行動に基づいた管理体制の構築が必要です。
(4) 勤怠集計作業が煩雑で時間がかかる
勤怠記録が紙やエクセルでバラバラに管理されていると、月末の集計作業に多くの手間がかかります。
勤務時間、残業時間、深夜勤務など、項目ごとの給与計算は煩雑です。
店舗数が多い企業では、データのとりまとめだけで1日仕事になることもあります。
ヒューマンエラーが避けられず、給与の計算ミスにもつながりかねません。
3. 課題別に見る勤怠管理システムによる解決策

飲食業の課題は、適切な勤怠管理システムを導入することで大きく改善できます。
勤怠管理システムには、現場の煩雑な業務を効率化し、ミスやトラブルを未然に防ぐ機能を備えています。
前述した課題ごとに、どのような機能が有効か整理しました。
- モバイル打刻で打刻ミスを防ぐ
- シフト連携機能で実働時間を可視化
- アラート通知で法令違反を防止
- 自動集計で集計ミス・作業負担を削減
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1) モバイル打刻で打刻ミスを防ぐ
スマートフォンを使った打刻機能を活用すれば、忙しい時間帯でも手軽に打刻できます。
たとえば個人の端末からシステムにログインするだけで打刻が完了する方式であれば、打刻忘れのリスクが大幅に減ります。
柔軟な打刻環境を整えることで、勤怠記録の精度が向上するでしょう。
(2) シフト連携機能で実働時間を可視化
勤怠管理システムとシフト表が連携していれば、予定と実績のズレがひと目で確認でき、労働時間の把握が容易になります。
「17:00退勤予定だったが、実際は18:10まで勤務」といった記録が自動で残るため、月末の確認作業が効率化されます。
管理者だけでなく、スタッフ自身も「自分の働いた時間」に対しての意識が高まるでしょう。
(3) アラート通知で法令違反を防止
勤怠管理システムには、残業時間の超過や休憩未取得、36協定の上限超えなどに対してアラートを出す機能が備わっているものも。
たとえば、週40時間を超える勤務が続いた場合に管理者へ通知するよう設定することで、法令違反の予防につながります。
忙しい現場でも法律を意識した労務管理が実現できるでしょう。
(4) 自動集計で集計ミス・作業負担を削減
月末にかかる勤怠の集計作業も、システム導入によって大幅に効率化されます。
出勤・退勤の打刻データを自動で反映し、残業・深夜・休憩・欠勤などもリアルタイムで集計可能。
手計算やエクセル入力の手間が不要になります。
ヒューマンエラーも起きづらくなり、給与計算や勤務実績の確認がスムーズに行えるようになるでしょう。
飲食業界に最適な勤怠管理システム「R-Kintai」

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。
徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。
打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。



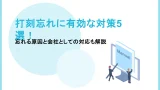

人気記事