シフト制で働く現場では、勤怠管理にまつわる悩みが尽きません。
「日によって勤務時間が違う」「急なシフト変更が多い」「複数店舗をまたぐスタッフがいる」といった状況が重なれば、集計ミスや打刻漏れが発生しやすくなります。
その結果、労働時間の把握が不正確になったり、残業時間の管理が曖昧になったりと、労務リスクが高まってしまう可能性も。
本記事では、シフト制の勤怠管理で起こりやすい課題から、効率化の具体策、勤怠管理システム導入のメリットや選定時の注意点まで、順を追ってわかりやすく解説します。
1.シフト制の勤怠管理でよくある課題とは?

小売業やサービス業など、シフト制の職場では、勤怠管理に悩みや手間がつきものです。
日ごとに勤務時間が異なる、複数拠点の情報をまとめにくいなど、管理者が抱える課題は多岐にわたります。
現場が忙しいほど、打刻ミスやシフトとのズレなどが発生しやすく、正確な勤怠把握が難しくなってしまうのが実情です。
ここでは、シフト制の勤怠管理でよく見られる代表的な課題を整理しました。
- 勤務時間が日によって異なるため集計が面倒
- 打刻忘れが起こりやすい
- シフトと実績のズレが見えにくい
- 複数店舗での管理が煩雑
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)勤務時間が日によって異なるため集計が面倒
シフト制では、日によって勤務時間が変動するため、集計作業に手間がかかります。
固定時間勤務のように単純な差し引き計算では対応できず、毎回勤務パターンを確認しながら処理する必要があるからです。
たとえば、「早番」「遅番」「通し勤務」といった多様なシフトを扱う職場では、管理者が手作業で確認・集計する場面が頻繁に発生します。
結果として、締め日前にミスが発覚し、修正に追われるケースも少なくありません。
(2)打刻忘れが起こりやすい
シフト勤務の現場では、出退勤時の打刻を忘れるケースが多くなりがちです。
繁忙時間帯や急な対応など、業務に追われて打刻が後回しになることが原因です。
レジや接客対応に入った直後に打刻を忘れ、そのまま1日が終わってしまうというトラブルは珍しくありません。
打刻ミスが頻発すると労働時間の正確な把握も難しくなります。
(3)シフトと実績のズレが見えにくい
シフト制の職場では、シフトと実際の勤務実績にズレが生じやすくなります。
そのズレが把握されないと、残業や早退、休憩の管理に支障が出る可能性も。
たとえば、15時までのシフトだったスタッフが、実際には17時まで働いていた場合、その差分が記録されずに見落とされます。
実績との乖離を放置すれば、残業代の未払いリスクにもつながりかねません。
(4)複数店舗での管理が煩雑
店舗ごとに運用ルールが異なる場合、勤怠情報の一元管理が非常に困難になります。
紙やExcelで店舗単位に管理していると、本部やエリアマネージャーが全体を把握しにくくなるためです。
たとえば、各店から勤怠データを回収し、1枚の管理表にまとめる作業が毎月の恒例業務になっている企業も少なくありません。
情報の分散は、管理効率だけでなく情報精度の低下も引き起こします。
2.シフト制の職場で勤怠管理を効率化する方法

シフト制の職場では、勤務時間や出勤パターンが多様なぶん、勤怠管理も複雑になりがちです。
紙やExcelでの管理を続けていると、打刻ミスや申請の確認漏れ、集計作業の負担といった問題が発生しやすくなります。
業務をスムーズに回すためには、現場に合った仕組みを取り入れ、手間やミスを最小限に抑える工夫が必要です。
ここでは、シフト制の職場で勤怠管理を効率化するための実践的な方法を紹介します。
- シフト情報と勤怠データを連動させる
- モバイル端末での打刻を導入する
- 申請・承認フローをデジタル化する
- 勤怠データをリアルタイムで集計・確認できる体制にする
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)シフト情報と勤怠データを連動させる
勤怠管理効率化には、シフト情報と実際の勤務データを連動させる仕組みが有効です。
手動の照合は手間がかかり、ミスの温床にもなりやすいため、連携機能のある仕組みを使うことがポイントです。
出勤予定と実績がリアルタイムで表示される機能があれば、遅刻や早退、残業の有無を一目で確認できます。
予定と実績のズレを管理者が即座に把握でき、対応のスピードも格段に上がるでしょう。
(2)モバイル端末での打刻を導入する
業務の合間に出退勤の打刻を行いやすくするには、スマートフォンやタブレットでのモバイル打刻が効果的です。
レジ業務や接客対応などで常に動き回るスタッフにとっては、設置型の打刻機では不便が生じがちです。
店舗のバックヤードや休憩スペースで手軽にスマホから打刻できるようにすれば、打刻忘れの防止にもつながります。
現場に合わせた柔軟な対応が、勤怠の正確性を保つカギになります。
(3)申請・承認フローをデジタル化する
休暇・残業・早退などの申請を紙でやり取りしている場合、管理負担が大きくなります。
記入漏れや回収遅れが発生しやすく、結果的に集計作業の遅延やミスにつながるためです。
システム上で申請から承認まで完結できれば、状況が一覧で確認でき、対応も迅速に。
アナログな手続きにかかる手間を減らすだけでも、大幅な業務改善が期待できるでしょう。
(4)勤怠データをリアルタイムで集計・確認できる体制にする
効率的な勤怠管理には、勤務データをリアルタイムで集計・確認できる仕組みが欠かせません。
締め日直前まで集計が進まず、慌ただしく処理を行う状況は、ミスの原因になります。
労働時間や残業時間を自動で可視化できるシステムを使えば、負担分散が可能です。
事務作業の簡略化だけでなく、現場とのコミュニケーションもスムーズになります。
3.勤怠管理システムを導入するメリット
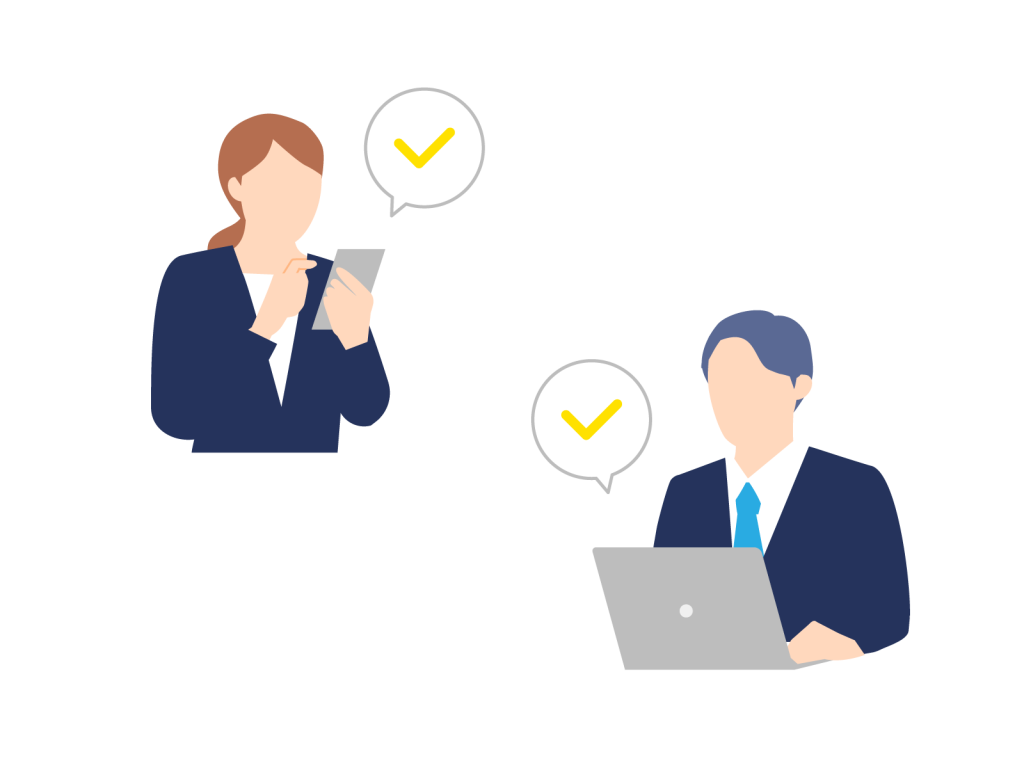
シフト制の職場では、日々の打刻や労働時間の把握、情報共有などが煩雑になりがちです。
これらを解消する方法として、導入が進んでいるのが「勤怠管理システム」です。
システム導入は、現場の負担軽減やミス削減にもつながります。
勤怠管理システムを導入することで得られる主なメリットを4つご紹介します。
- 打刻ミスや集計ミスの削減
- 残業時間や労働時間の自動把握
- 店舗間での情報共有がスムーズになる
- スタッフの働き方の見える化が進む
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)打刻ミスや集計ミスの削減
勤怠管理システムを導入することで、手作業によるミスのリスクを大幅に減らせます。
手書きやExcelでの運用では、入力漏れや数式エラーなどが起きやすく、確認にも時間がかかりがちです。
出退勤が自動で記録・集計に反映される仕組みであれば、手作業を最小限に抑えられます。
結果として、精度の高い勤怠管理が可能になり、確認作業の負担も軽減されるでしょう。
(2)残業時間や労働時間の自動把握
システムを使えば、各スタッフの労働時間や残業時間を自動的に把握できます。
現場での過重労働や36協定の上限超過といったリスクにも素早く気づくことができます。
週ごとの残業時間が可視化されれば、事前の調整が可能になり、無理のない働き方をサポートできます。
健康管理と法令遵守の両立につながる大きなメリットといえるでしょう。
(3)店舗間での情報共有がスムーズになる
複数店舗を運営する企業では、勤怠データの集約・確認に時間がかかるケースが多く見られます。
勤怠管理システムなら、店舗ごとの勤怠状況をリアルタイムで本部が確認できます。
他店舗応援や急な欠勤など、店舗をまたいだ調整が必要な場合でも、状況を即座に共有できると判断が早まります。
全体最適の視点で運営判断ができる体制を整えるうえでも、有効な手段です。
(4)スタッフの働き方の見える化が進む
勤怠システムには、一人ひとりの勤務実績や残業傾向がデータとして蓄積されます。
感覚ではなく、事実に基づいたマネジメントができるようになるのが大きな利点です。
たとえば、「いつも遅番に偏っている」「連勤が続いている」といった状況が明らかになれば、早期のシフト見直しや声かけが可能になります。
公平性のある働き方を実感しやすくなるでしょう。
4.シフト制の職場に合った勤怠管理システムの選び方

勤怠管理システムを「有名だから」「機能が多いから」といった理由で選ぶのは危険です。
とくにシフト制の職場では、勤務形態や現場の動き方が多様なため、実際のオペレーションに合ったシステムでなければ活用されにくくなります。
混乱や負担を生まないよう、導入前にしっかりと確認すべきポイントがあります。
シフト制の現場に適した勤怠管理システムを選ぶ注意点を4つにまとめました。
- 現場のオペレーションに合っているか
- シフト・勤怠が一元化できるか
- 複数拠点管理がしやすいか
- サポートや導入時の負担はどうか
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)現場のオペレーションに合っているか
まず確認すべきなのは、現場の運用に無理なくフィットするかどうかです。
機能が豊富でも、実際の業務に合わなければ使われずに終わる可能性があります。
たとえば、スタッフがスマホで打刻したい現場でPC専用システムを導入しても、運用が定着しにくくなります。
導入前には実際の業務フローと照らし合わせ、活用できるか検討することが重要です。
(2)シフト・勤怠が一元化できるか
シフト作成と勤怠管理がバラバラだと、確認や集計の手間が大きくなり、ミスも発生しやすくなります。
同じシステム内でシフトと勤怠を一元的に管理できるかは、導入時の大きな判断基準です。
たとえば、シフトと出退勤実績が自動で連携される仕組みなら、集計作業の大幅な効率化が期待できます。
情報の分散を防ぐことで、業務のスピードと精度の両方が向上するでしょう。
(3)複数拠点管理がしやすいか
シフト制の職場では、複数拠点をまたいでスタッフが働くケースも珍しくありません。
各店舗の状況を一元的に把握できるかどうかは非常に重要です。
エリアマネージャーが全店の勤怠状況を一つの画面で確認できれば、応援依頼や配置調整もスムーズになります。
拠点ごとに別々に運用するより、全体を見渡せる管理体制が業務効率を大きく左右します。
(4)サポートや導入時の負担はどうか
機能が優れていても、初期設定や導入時の説明に負担がかかるようでは現場に定着しません。
ITに不慣れなスタッフが多い現場では、導入しやすさやサポート体制が成功のカギを握ります。
導入初期に手厚いサポートが用意されていれば、不安なく使い始めることができます。
現場が「これなら使える」と思えるかどうかが、使い続けられるかを左右します。
シフト制に最適化した勤怠管理システム「R-Kintai」

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。
徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。
打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。

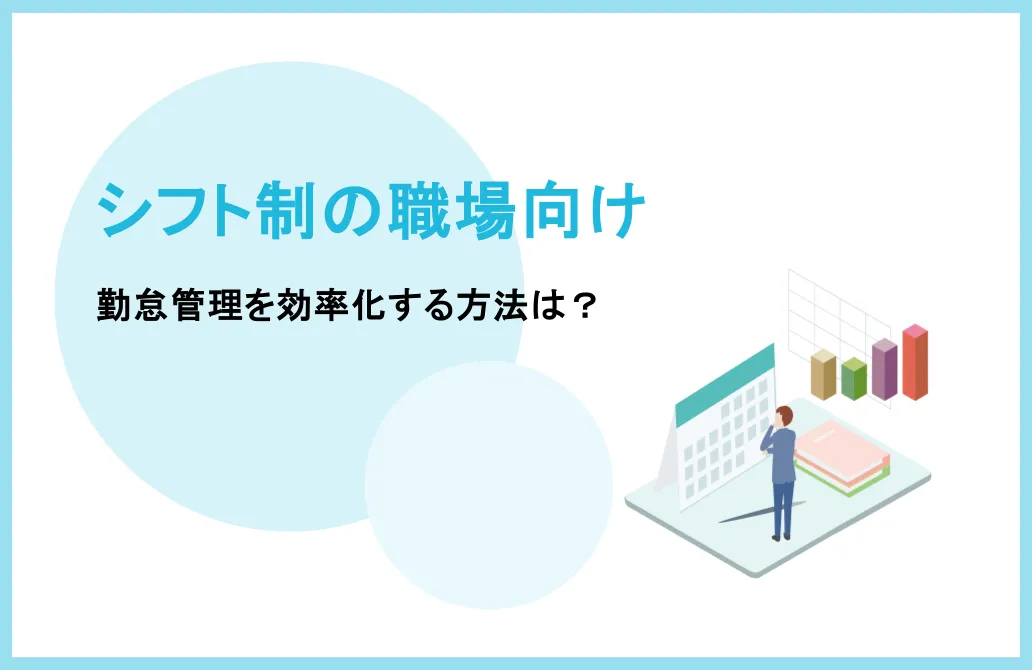



人気記事