勤怠管理を効率化したいけれど、「まずはコストをかけずに始めたい」「でも機能が物足りなかったらどうしよう」と迷っていませんか?
無料で使える勤怠管理アプリは多くの企業にとって魅力的な選択肢です。
しかし業務内容や組織の規模によっては「有料版にしておけばよかった…」と感じることもあります。
本記事では、無料アプリと有料アプリの違いや選び方のポイントをわかりやすく解説しつつ、実際に使える無料勤怠管理アプリ5選を紹介します。
1.勤怠管理アプリ・無料と有料の違い
勤怠管理アプリを選ぶ際、「無料で使えるものがあるなら、わざわざ有料を選ぶ必要はあるのか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
確かに無料アプリは導入のハードルが低く、気軽に試せる点が魅力です。
しかし、機能の制限やサポート体制、利用できる人数など、有料版とは異なります。
ここでは、無料版と有料版それぞれの違いについて具体的に確認していきましょう。
・使える機能の幅に差がある
・サポート体制や導入支援の有無
・カスタマイズや連携の柔軟性
・無料版は使用できる人数に限りがある
以下、それぞれについてまとめました。
(1)使える機能の幅に差がある
勤怠管理アプリの無料版と有料版では、使える機能の範囲に大きな違いがあります。
無料版では打刻や勤怠の基本的な記録機能に限定されていることが多く、シフト管理や給与計算との連携などは対応していないケースがほとんどです。
無料アプリでは「出退勤の記録」はできても「複数拠点の一括管理」や「管理者の承認フロー」には非対応という例がよくあります。
運用にあたって求める機能が明確な場合は、有料版の方が柔軟に対応できる可能性が高いでしょう。
(2)サポート体制や導入支援の有無
有料アプリには、導入支援や継続的なサポート体制が整っているという強みがあります。
無料アプリではトラブルが発生しても基本的には自己解決が求められるため、ITに不慣れな企業や人手の少ない現場では負担になりやすいです。
「打刻がうまくいかない」「設定が分からない」といった場面で、チャットサポートや導入ガイドがあるかどうかで対応スピードが大きく変わってきます。
困ったときにすぐ相談できる環境は、スムーズな運用の大きな安心材料になります。
(3)カスタマイズや連携の柔軟性
業務に合わせたカスタマイズや他システムとの連携機能は、有料版に軍配が上がります。
無料アプリではあらかじめ用意された機能しか使えないことが多く、業務フローに完全には適合しない場合もあります。
有料アプリでは勤怠データを会計ソフトや給与計算ソフトに自動連携させられる一方、無料アプリではCSV出力すら制限されるケースもあります。
業務全体の効率化を目指すなら、連携性や柔軟性は欠かせない視点です。
(4)無料版は使用できる人数に限りがある
無料版は、ユーザー数に上限が設定されていることが一般的です。
提供企業がコストを抑えながらサービスを運営しているためです。
一定以上の利用は有料プランへ誘導する仕組みになっています。
たとえば、「5名まで無料」「10名以上は有料プランが必要」といった制限があり、店舗スタッフが多い現場では途中から使えなくなるケースもあります。
利用人数が増える見込みがあるなら、最初から有料プランの検討を視野に入れておいた方がスムーズです。
2.無料の勤怠管理アプリを使うメリット

「コストをかけずに勤怠管理を始めたい」「まずは気軽に試してみたい」
――そんなニーズに応えてくれるのが、無料の勤怠管理アプリです。
最低限の機能に絞られている分、導入や運用もシンプルで、小規模な職場やスタートアップ企業でも無理なく利用できます。
ここでは、無料アプリならではのメリットを具体的に紹介します。
・コストをかけずに導入できる
・操作がシンプルで使いやすい
・トライアルとして利用しやすい
以下、それぞれについてまとめました。
(1)コストをかけずに導入できる
無料アプリの最大のメリットは、導入コストがかからない点です。
勤怠管理を改善したくても、費用面のハードルから導入をためらうケースは少なくありません。
個人経営の飲食店や小規模オフィスでは、「まずは無料で試せるなら使ってみよう」という判断がしやすくなります。
初期費用がゼロであれば、気軽に始められる分、勤怠管理の一歩を踏み出しやすくなります。
(2)操作がシンプルで使いやすい
多くの無料勤怠管理アプリは、必要最低限の機能に絞られており、シンプルで直感的な操作が可能です。
不慣れなスタッフでもスムーズに使い始めやすく、導入初日から実務に活かせることが多いです。
たとえば、「出勤ボタンを押すだけ」といった操作画面であれば、アルバイトやパートでもすぐに慣れることができます。
複雑な設定がいらない分、現場への浸透もスムーズに進みやすいのが特徴です。
(3)トライアルとして利用しやすい
無料アプリは「本格導入の前に使ってみる」という目的にも適しています。
導入前に実際の運用に合うかを確かめられるため、選定ミスによる時間やコストのロスを防ぎやすくなります。
たとえば、いくつかの無料アプリを比較し、操作性や機能の違いを体感したうえで、有料プランへの移行を判断できるのは大きな利点です。
事前に試せることで、後悔のない選択につながりやすくなります。
3.無料勤怠アプリを使うデメリット

無料アプリには魅力も多い一方で、導入後に「思ったより使いにくい」「この機能が足りない」と感じることもあります。
とくに利用人数の制限やサポートの有無、機能の限界は、実務で使ううちにストレスとなることも少なくありません。
ここでは、無料アプリを選ぶ際に注意したい主なデメリットについて解説します。
・機能が制限されていることが多い
・サポートが受けられない・対応が遅い
以下、それぞれについてまとめました。
(1)機能が制限されている
無料の勤怠アプリは、基本的な機能に限られていることがほとんどです。
たとえば、打刻や勤怠記録はできても、シフト作成や給与計算との連携ができないケースが多く、業務全体をカバーしきれません。
たとえば「出退勤の記録はできるが、有休の申請や残業時間の自動集計はできない」といった制限があるアプリも珍しくありません。
また、情報の保存期間が半年分まで、csvで出力できない、などの制限もあります。
使っていく中で「これもできたらいいのに」と感じる場面が増えるでしょう。
(2)サポートが受けられない・対応が遅い
無料アプリは、有料プランと比べてサポート体制が不十分なことが多いです。
問題が起きたときにすぐに問い合わせができなかったり、そもそもサポート対象外という場合もあります。
たとえば、設定ミスで全員の勤怠が記録できなかったとしても、自分で原因を調べて解決する必要があるケースも考えられます。
トラブル時にすぐ対応できないことは、現場の混乱や作業の遅れにつながるリスクとなります。
4.無料の勤怠管理アプリ最新おすすめ5選

勤怠管理を始めたいけれど「コストはなるべくかけたくない」「まずは使いやすいものを試したい」と考える企業や個人事業主は少なくありません。
そんなニーズに応えてくれるのが、スマホやタブレットから手軽に使える無料の勤怠管理アプリです。
近年では、出退勤の打刻はもちろん、シフト管理や給与の簡易計算など、多機能なアプリも登場しています。
ここでは、スマホで使える無料の勤怠管理アプリの中から、特に注目されている5つのサービスを厳選してご紹介します。
・タブレット タイムレコーダー
・マネーフォワードクラウド勤怠
・スマレジ・タイムカード
・勤務ろぐ
・タイムシート
以下、それぞれについてまとめました。
(1)タブレット タイムレコーダー
iPadをタイムレコーダーにするアプリ。
月額無料で勤怠管理ができます。
打刻時の写真やビデオメッセージなどの機能があり、勤怠管理以外に学習塾や習い事の出席確認にも使われています。
・初期費用:月額費無料(3名まで)
・利用人数10名毎に11,800円でライセンス購入
公式サイトはこちら
タブレット タイムレコーダー
(2)マネーフォワードクラウド勤怠
裁量労働制やフレックスタイム制などに対応した勤怠管理システム。
マネーフォワードシリーズの給与計算や会計システムとも連携できます。
初期費用:0円(51名以上の場合有料)
月額費用:税抜900円~(個人向け)税抜2,980円~(法人向け)
公式サイトはこちら
マネーフォワードクラウド勤怠
(3)スマレジ・タイムカード
登録店舗数14万件以上のクラウド勤怠管理システム。
勤怠管理やシフト管理の機能があります。
60日間無料お試しが可能です。
初期費用0円
勤怠管理のみの場合は30名まで0円
公式サイトはこちら
スマレジ・タイムカード
(4)勤務ろぐ
個人向けの無料勤怠管理アプリで、勤務時間や残業時間などを記録できます。
シフト制にも対応しており、勤務時間をパターン登録できます。
初期費用:0円
月額費用:0円
アプリのインストールはこちら
勤務ろぐ (勤怠,出退勤管理) – Google Play のアプリ
(5)タイムシート
アプリ内の「出勤」「退勤」ボタンで簡単に勤怠記録がつけられる無料アプリ。
時給や日給の登録もできるので、アルバイトをしている人にもおすすめです。
初期費用:0円
月額費用:0円
アプリのインストールはこちら
「簡単入力!!「タイムシート」」iOS向けApp Store
簡単入力!!「タイムシート ライト」 – Google Play のアプリ
5.無料の勤怠管理アプリに向いている企業の特徴

勤怠管理アプリを検討する際、無料プランが自社に合っているのかどうかを見極めることが重要です。
無料アプリはコストを抑えられる一方で、機能やサポートに制限があるため、すべての企業にとって最適とは限りません。
ここでは、無料の勤怠管理アプリを有効に活用できる、比較的向いている企業の特徴を紹介します。
・従業員数が少ない
・シフトがあまり複雑でない
・勤怠管理アプリをまずは試したいだけ
以下、それぞれについてまとめました。
(1)従業員数が少ない
無料の勤怠管理アプリは、少人数のチームや事業所に特に向いています。
多くの無料プランでは「5人まで」「10人まで」など利用人数に制限があります。
少人数であれば機能制限の影響を受けずに使えるでしょう。
たとえば、個人経営の店舗や5人前後のスタートアップ企業では、無料アプリでも十分に日常業務をカバーできるケースが多くあります。
コストを抑えながら基本的な勤怠管理を実現したい企業には、無料プランがフィットしやすいです。
(2)シフトがあまり複雑でない
複雑なシフト管理が不要な業務形態では、無料アプリでも問題なく運用できます。
固定時間勤務であれば、高度な設定や自動調整機能がなくても業務が回るでしょう。
たとえば、平日9〜17時勤務のスタッフが数名という職場では、基本的な打刻と勤務記録さえできれば十分な管理が可能です。
業務内容が単純で調整の手間が少ない現場には、操作も簡単な無料アプリが適しています。
(3)勤怠管理アプリをまずは試したいだけ
本格導入の前に勤怠管理の流れを把握したい企業にとって、無料アプリは最適な選択肢です。
有料ツールをいきなり導入するより、まずは無料版で操作感や使い勝手を体験しておくことで、後悔のない選定につながります。
たとえば、2〜3カ月間無料アプリで運用してみて「もっと機能が欲しい」と感じたら有料版にスムーズに移行する流れも可能です。
まずは手軽に始めてから段階的にシステムを強化したい場合、無料アプリの活用は非常に有効です。
6.有料の勤怠管理アプリが選ばれる理由
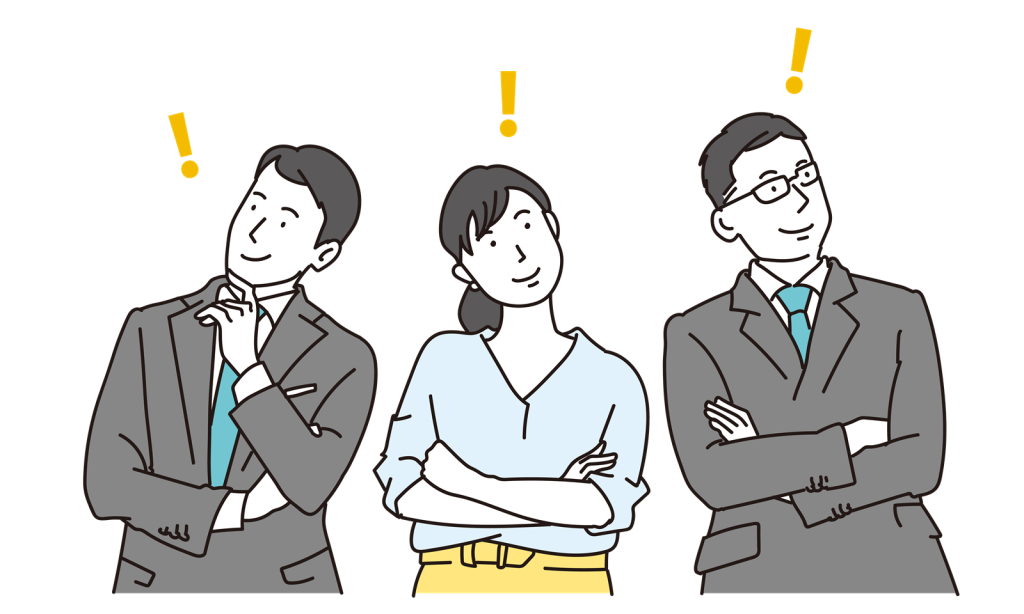
コストを抑えられる無料アプリに対して、有料の勤怠管理アプリは「機能性」や「運用のしやすさ」で多くの企業に選ばれています。
とくに従業員数が多い、シフトが複雑、給与や労務とも連携したいといったニーズがある場合、有料プランの方が業務負担を大幅に軽減できます。
ここでは、有料アプリが選ばれる主な理由を見ていきましょう。
・サポート体制や導入支援が手厚い
・シフト・給与・労務などと連携しやすい
・業態に合わせたカスタマイズやスケールアップが可能
以下、それぞれについてまとめました。
(1)サポート体制や導入支援が手厚い
有料の勤怠管理アプリは、初期導入から運用まで一貫したサポートが受けられるのが大きな特徴です。
無料アプリでは自己解決が基本ですが、有料プランでは設定支援・導入研修・チャット対応などのサポート体制が整っています。
「導入後に操作方法がわからなくなった」といった場面でも、専門スタッフにすぐ相談できることで安心して運用が継続できます。
トラブル時に頼れるサポートがあることは、企業全体の勤怠管理の安定にもつながります。
(2)シフト・給与・労務などと連携しやすい
有料アプリは、勤怠だけでなく他の管理業務との連携にも優れています。
給与計算や労務管理ツールとデータを自動連携できるため、手入力や集計の手間を大幅に減らすことが可能です。
勤怠データが自動で給与ソフトに反映されることで、締め作業が効率化され、ミスのリスクも軽減されます。
業務全体の流れをつなぐシステムとして、連携性は非常に重要なポイントです。
(3)業態に合わせたカスタマイズやスケールアップが可能
有料アプリの強みのひとつが、業種や組織規模に応じた柔軟な対応力です。
飲食・医療・小売など、それぞれの現場で必要とされる機能をカスタマイズでき、従業員数が増えてもスムーズに拡張できます。
店舗数の拡大や多拠点管理が必要になった場合でも、同じシステム内で対応できるため、再選定の手間がかかりません。
長期的に安心して使い続けたい企業にとって、拡張性の高さは大きな魅力となります。
シフト管理と勤怠管理の両立なら「R-Kintai」

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。
徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。
打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。

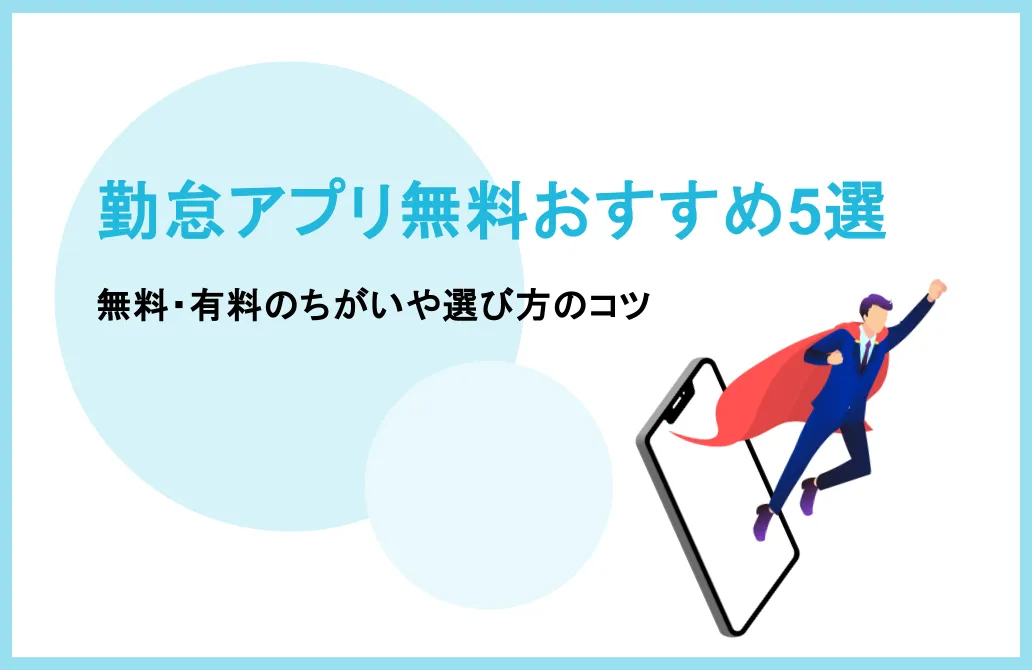

人気記事