テレワークの普及により、場所を選ばず働ける環境が整いつつありますが、その一方で「勤怠管理が難しい」と感じる企業も増えています。
オフィスに出社していたときには見えていた勤務状況が、在宅勤務では把握しづらくなり、管理者・従業員双方にとってストレスになるケースも少なくありません。
では、テレワークにおける勤怠管理はどのように行えばよいのでしょうか?
本記事では、テレワーク特有の課題や管理方法の選び方、システム活用のコツまでをわかりやすく解説します。
1.テレワークの勤怠管理でよくある課題
テレワークが広がる中で、勤怠管理の難しさを感じている企業は少なくありません。
これまでオフィスで行っていた管理方法が通用しにくくなり、新たな課題が浮き彫りになってきました。
ここでは、テレワークにおいて特に多くの企業が直面している代表的な課題を紹介します。
・勤務時間の把握が難しい
・働きすぎのリスク
・サボりの懸念
・打刻ミス・報告漏れ
・管理者側の負担増
以下、それぞれについてまとめました。
(1)勤務時間の把握が難しい
テレワークでは、従業員の勤務時間を正確に把握するのが困難です。
出社時と異なり、始業・終業のタイミングを目視で確認できないため、勤務実態が見えにくくなります。
仕事を始める前に家事を済ませていたり、業務の合間に私用を挟んでいたりしても、把握しきれないことがあります。
勤務状況の不透明さが課題となるため、適切な仕組みづくりが重要になります。
(2)働きすぎのリスク
テレワークでは、従業員が働きすぎてしまうリスクがあります。
オフィスと違い、終業時間に気づきにくく、つい長時間働いてしまう傾向があるためです。
集中して作業していたらいつの間にか定時を過ぎていたり、休憩を取らずに業務を続けてしまったりするケースがあります。
働きすぎは、健康被害や生産性の低下にもつながります。
適切な勤怠管理でオン・オフの切り替えをサポートすることが重要です。
(3)不正打刻(サボり)の懸念
テレワークでは、従業員の勤務実態が見えにくいため、不正打刻(いわゆるサボり)への懸念も拭えません。
自己管理が難しい環境では、業務のメリハリがつかず、集中力の維持が課題になります。
たとえば、動画を見たり、私用の電話を長時間していたりと、勤務時間中に業務と関係のない行動を取る可能性も否定できません。
こうした事態を防ぐためには、成果ベースの評価や、勤務状況の可視化ができるシステムの導入が有効です。
(4)打刻ミス・報告漏れ
テレワークでは、打刻ミスや勤怠の報告漏れが発生しやすくなります。
これは、業務に集中するあまり打刻を忘れたり、ツールの操作に不慣れだったりすることが原因です。
たとえば、チャットやメールでの報告に頼っている場合、送信を忘れていたり、情報が記録として残りにくいといった問題があります。
正確な勤怠情報を管理するためには、打刻忘れを防ぐ仕組みや、操作しやすいツールの導入が有効です。
(5)管理者側の負担増
テレワーク下では、勤怠情報の収集や確認にかかる管理者の負担が増加しがちです。
理由は、従業員の働き方が多様化し、個別対応や確認作業が煩雑になるためです。
手動で出退勤時間を確認して集計していると、ミスや確認漏れが発生しやすく、管理コストが高まります。
管理業務の負担を軽減するためにも、リアルタイムで勤怠状況を確認できる仕組みの導入が鍵となります。
2.テレワーク中の勤怠管理方法は?
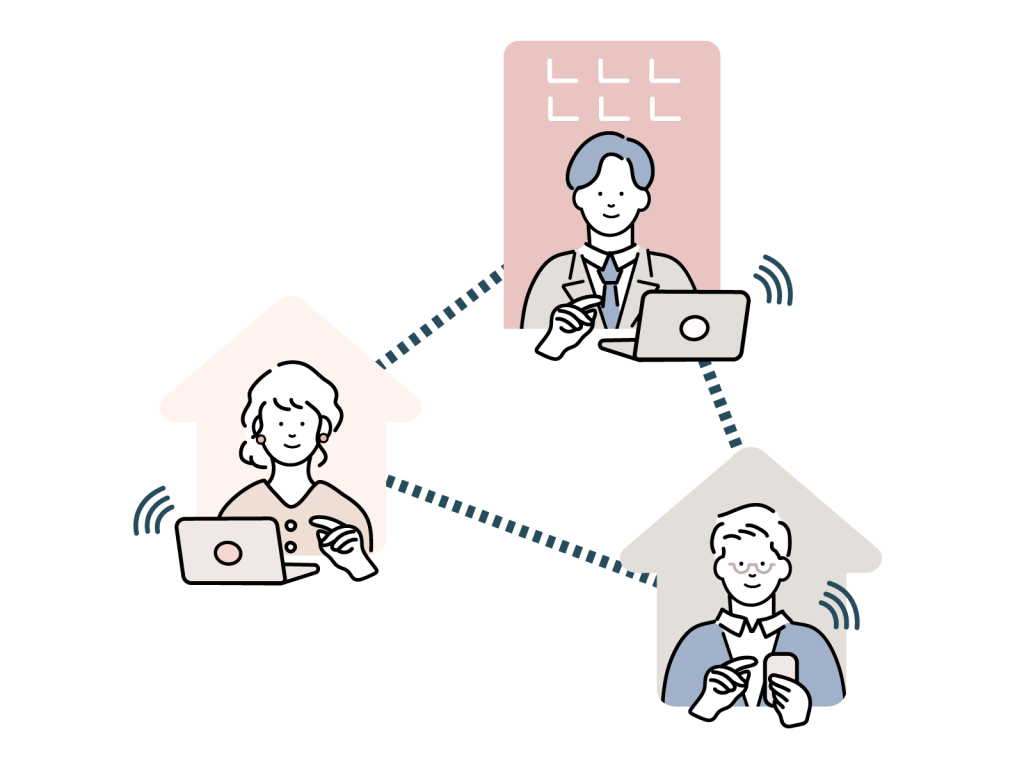
テレワークに対応する勤怠管理の方法には、いくつかの選択肢があります。
ただし、どの方法にもメリットとデメリットがあり、業務に合った手段を選ばなければ管理負担が増えてしまう恐れも。
以下、代表的な管理手段とその特徴を比較しながら、より効果的な勤怠管理の方法について解説します。
(1)Excelやスプレッドシートを使うのは手間
テレワークの勤怠管理にExcelやスプレッドシートを使う方法は、手間がかかります。
記入ミスや入力漏れが起きやすく、手動での集計や確認作業が必要です。
従業員が毎日各自で入力していても、管理者側が内容を確認・修正する手間が発生し、全体の作業負担が大きくなります。
その結果、正確性や効率性に欠けてしまうため、長期的に見て継続しにくい方法と言えるでしょう。
(2)メールで報告するのも管理が難しい
メールで勤怠を報告する方法も、管理の面で課題が多くあります。
報告が個別に届くため、情報が分散してしまい、集計や確認作業に多くの時間を要するからです。
毎朝複数のメールを受け取って、管理者が手作業でまとめるケースでは、見落としやミスが起きやすくなります。
情報が一元管理できない方法では、勤怠の把握や記録に時間がかかり、業務効率を損なう原因になるでしょう。
(3)勤怠管理システムの活用がベスト
テレワークの勤怠管理には、専用の勤怠管理システムを活用するのが最も効率的です。
自動打刻やリアルタイム集計、エラー検知などの機能があり、正確でスムーズな勤怠管理が可能になるためです。
Web打刻やGPS機能を使えば、どこからでも正確に出退勤を記録でき、管理者も状況をリアルタイムで把握できます。
システムを導入することで手間やミスを減らせるだけでなく、従業員の働き方に合った柔軟な管理が実現できるでしょう。
3.テレワークに向いている勤怠管理システムの特徴
テレワークでの勤怠管理をスムーズに行うためには、システム選びが非常に重要です。
どのシステムを選ぶかによって、管理者の負担や従業員の働きやすさが大きく変わってきます。
特にテレワークに対応するうえで押さえておきたい機能を備えたシステムなら、勤怠管理の精度と効率がともに向上します。
ここでは、テレワークに適した勤怠管理システムに共通する主な特徴をご紹介します。
・Web打刻・GPS打刻ができる
・リアルタイムで勤務状況が確認できる
・シフト・残業・休暇も一元管理できる
以下、それぞれについてまとめました。
(1)Web打刻・GPS打刻ができる
テレワークには、Web打刻やGPS打刻の機能が欠かせません。
どこにいても正確に出退勤を記録できることで、勤務状況の信頼性が高まるためです。
自宅や外出先からスマートフォンやPCを使って簡単に打刻でき、打刻時の位置情報も管理者が確認できます。
この機能があれば、出社が前提でなくてもスムーズな勤怠管理が可能になります。
(2)リアルタイムで勤務状況が確認できる
勤怠管理システムは、リアルタイムで勤務状況を把握できることが求められます。
理由は、テレワークでは従業員の働き方が見えにくくなるため、進捗や稼働状況の把握が困難になるからです。
出退勤だけでなく、現在誰が勤務中か、何時間働いているかがリアルタイムで一覧できれば、管理者側も安心です。
見える化によって、従業員との信頼関係や適切な業務配分の実現につながります。
(3)シフト・残業・休暇も一元管理できる
テレワークに対応するには、勤怠だけでなくシフトや残業、休暇などもまとめて管理できることが望まれます。
なぜなら、複数の管理ツールを使い分けると、確認や集計の手間が増え、情報の見落としや二重入力のリスクがあるためです。
一つのシステム上でシフト作成・残業申請・有休管理まで完結すれば、管理者も従業員も手間なく運用できます。
業務を効率化しつつ、ミスのない勤怠管理を実現するには、一元管理が効果的です。
4.テレワークの勤怠管理で失敗しないためのポイント
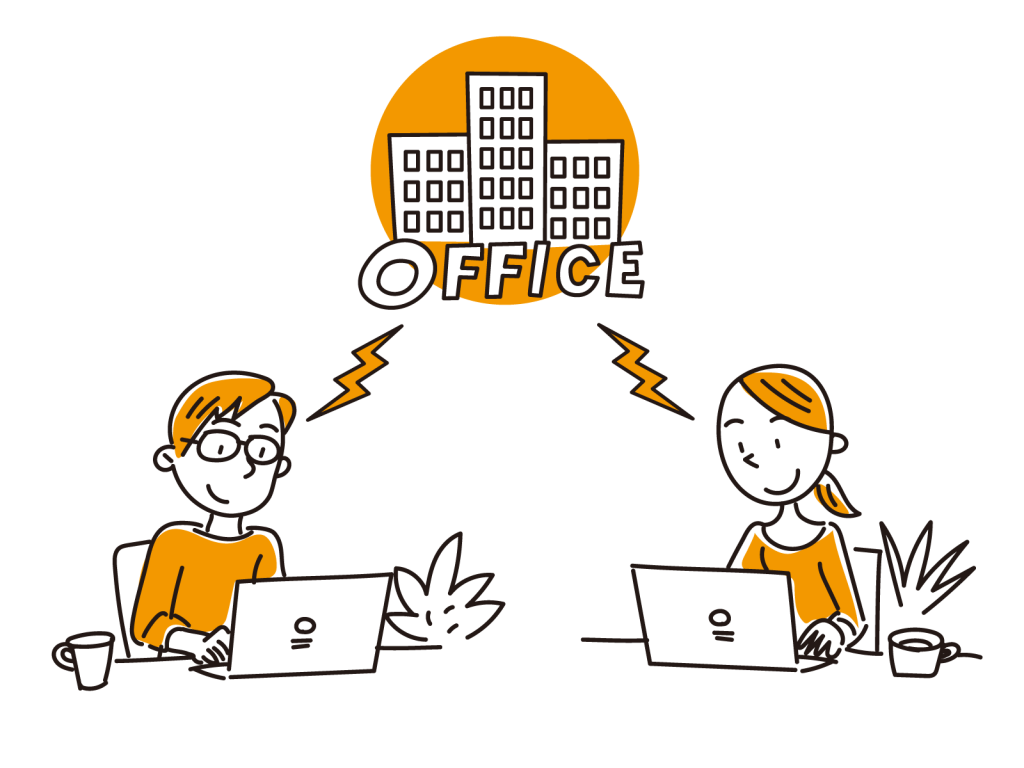
どんなに優れた勤怠管理システムを導入しても、運用方法を誤ればうまく機能しません。
特にテレワークでは、従業員との距離がある分、管理の仕組みやルールの整備が一層重要になります。
テレワークでも安心して勤怠管理を行うために押さえておきたい、実践的なポイントを紹介します。
・従業員に負担のない仕組みを選ぶ
・勤怠ルールを明確にし、共有する
・定期的な意見交換の場を設ける
以下、それぞれについてまとめました。
(1)従業員に負担のない仕組みを選ぶ
テレワークでの勤怠管理には、従業員にとって使いやすい仕組みを選ぶことが大切です。
操作が複雑だったり手間がかかるシステムでは、打刻ミスや入力忘れが増える恐れがあるためです。
たとえば、スマホやパソコンから簡単に打刻できるシステムであれば、外出先や自宅からでもスムーズに対応できます。
従業員の負担を最小限に抑えることで、勤怠データの正確性と運用の継続性が確保されます。
(2)勤怠ルールを明確にし、共有する
勤怠ルールを明確にし、全員に共有することは、トラブルを防ぐ基本です。
テレワークでは判断基準が曖昧になる場面も多く、ルールが統一されていないと混乱が生じます。
「出勤の定義」や「中抜けの扱い」などを定め、社内FAQとして共有しておけば、誤解を防げます。
ルールを明文化し、全員が同じ理解を持つことで、勤怠管理の質も向上します。
(3)定期的な意見交換の場を設ける
テレワーク環境では、勤怠管理に関する課題や不満が表に出にくくなります。
だからこそ、従業員の声を聞ける場を定期的に設けることが重要です。
月に一度のオンラインミーティングで勤怠管理に関する意見を募ったり、匿名のアンケートを実施したりすることで、改善点が見えてきます。
一方通行ではなく、双方向のやりとりができる環境づくりが、制度の定着と職場全体の満足度向上につながります。
多様な働き方に対応する「R-Kintai」

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。
徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。
打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。

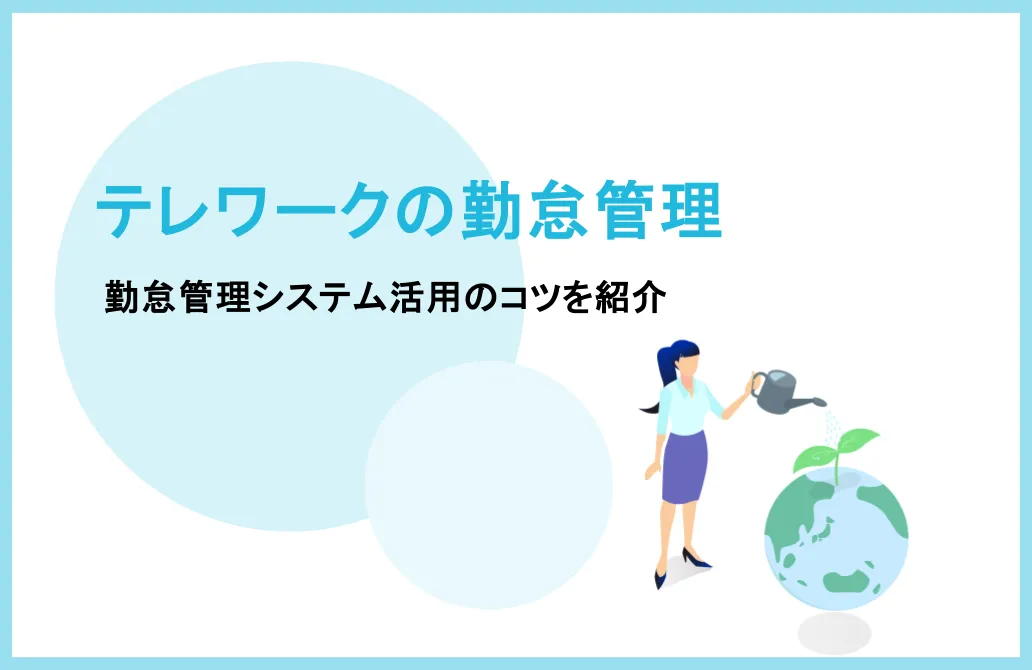

人気記事