製造業では、シフト勤務や工場ごとのルールなどが絡み合い、勤怠管理が複雑になりがちです。
紙や手書きでの対応では、集計ミスや法令違反のリスクも高まります。
この記事では、製造業の勤怠管理でよくある課題とその解決策、そしてシステム導入によるメリットについてわかりやすく紹介します。
1.製造業において勤怠管理が重要な理由とは
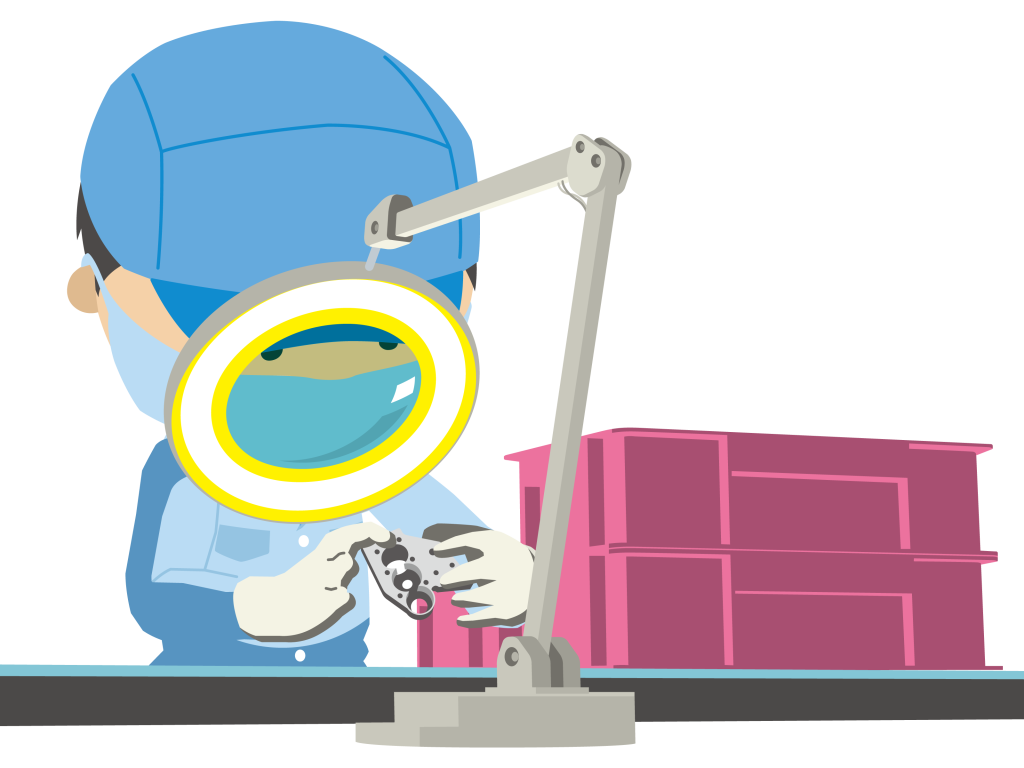
製造業では、勤務形態が多様であり、工程ごとの人員配置が製品品質や生産性に直結します。
また、交代制勤務が日常的であるため、労働時間や休憩時間の適正な管理が必要です。
適切な勤怠管理を行うことは、企業にとって必須の取り組みといえるでしょう。
主に以下の3点が、製造業において勤怠管理の重要性を高めています。
- 生産計画と人員配置の最適化のため
- シフト制・交代制勤務の管理が複雑だから
- 労働時間・残業時間の法令遵守が求められるから
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)生産計画と人員配置の最適化のため
生産性を維持するには、必要な人員を適切なタイミングで配置することが重要です。
勤怠管理がしっかりしていれば、各ラインや時間帯における稼働状況を把握しやすくなります。
欠勤者が出た際のフォローや、繁忙期の増員調整などもスムーズになります。
人手不足による生産遅延や、無駄な人員配置によるコスト増加を防ぐことができるでしょう。
(2)シフト制・交代制勤務の管理が複雑だから
製造業では日勤・夜勤を含む交代制勤務が一般的です。
このような勤務形態では、出退勤時間や休憩時間の管理が煩雑になりがちです。
たとえば、日をまたいで勤務するケースでは、どこまでが前日勤務でどこからが当日勤務か、あいまいになりやすいという課題があります。
勤怠管理をシステム化することで、時間管理のズレを防ぎ、労働実態を正確に記録することが可能になります。
(3)労働時間・残業時間の法令遵守が求められるから
働き方改革関連法の施行により、労働時間の上限や割増賃金の計算などが厳格に求められています。
製造業では繁忙期に残業が集中しやすく、適正な管理を怠ると法令違反につながる恐れも。
勤怠管理システムを活用すれば、リアルタイムで残業時間をチェックできるため、過重労働の抑制にもつながります。
2.製造業でよくある勤怠管理の課題
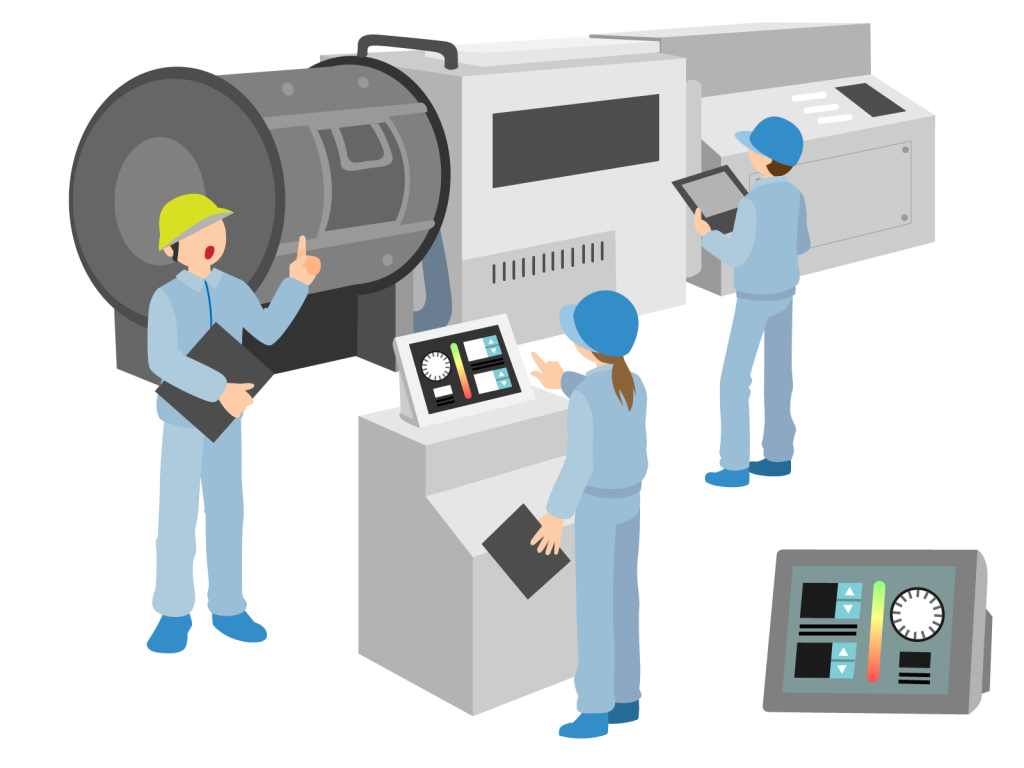
製造業では、現場ごとの作業特性や勤務体系により、勤怠管理に関する課題が発生しやすい傾向があります。
特に、紙ベースの運用が残っている場合、入力ミスや記録漏れなどのリスクが高まります。
現場の多くが交代制・シフト制であることも、時間管理の複雑さを助長する要因です。
ここでは、製造業でよく見られる勤怠管理上の課題を4つまとめました。
- 出退勤記録の漏れや不正打刻
- シフト管理と実績とのズレ
- 紙・Excelでの管理による非効率
- 管理者の負担が大きい
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)出退勤記録の漏れや不正打刻
勤怠管理の基本である打刻が、正しく行われていないケースは少なくありません。
打刻忘れや、同僚による代理打刻などがこれに該当します。
紙のタイムカードやアナログな打刻機では、こうした不正を防ぎきるのが難しいというのが現実です。
実際の労働時間と記録が一致しない事態が発生し、給与計算ミスや法的リスクにつながる恐れがあります。
(2)シフト管理と実績とのズレ
予定されたシフトと実際の勤務時間が食い違うことも、現場ではよく起こります。
急な残業や早退、休憩の取り方が計画通りにいかないことがあり、管理側が追いきれないという問題があります。
残業代の支払いや労働時間集計が不正確になり、トラブルにつながるケースもあるかもしれません。
(3)紙・Excelでの管理による非効率
依然として紙のタイムカードやExcelで勤怠管理をしている現場も多く見られます。
こうした方法では、転記ミスやファイルの属人化が起きやすく、全体の作業効率を著しく低下させます。
集計やチェック作業に時間を要し、リアルタイムな対応が難しくなるのもデメリットです。
(4)管理者の負担が大きい
手作業中心の勤怠管理では、管理者の負担が非常に大きくなります。
シフト調整や勤務状況の確認に多くの時間を取られ、本来の業務に集中できない状況が発生しがちです。
トラブルが発生した際の対応や調査にも工数がかかるため、業務全体の非効率にもつながります。
3.課題別に見る勤怠管理の解決策

前章で紹介したように、製造業における勤怠管理にはさまざまな課題があります。
それらの課題に対しては、適切な仕組みやツールを導入することで、効率化とトラブル防止の両立が可能です。
ここでは、課題ごとに効果的な解決策を取り上げて解説します。
- 生産現場の出退勤データを正確に取得する方法
- シフトとの乖離をリアルタイムで把握する工夫
- 手作業の勤怠集計をデジタル化する手段
- 管理者の負担を減らす自動化の導入
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)生産現場の出退勤データを正確に取得する方法
正確な打刻データの収集は、勤怠管理の土台です。
顔認証やICカード、スマホ打刻を導入すれば、不正や記録漏れを防ぐことができます。
たとえば、顔認証による打刻であれば、なりすましによる打刻ミスも防止でき、確実な本人認証が可能に。
結果として、給与計算や労務管理の精度向上につながるでしょう。
(2)シフトとの乖離をリアルタイムで把握する工夫
予定シフトと実働時間のズレを早期に把握することは、過重労働の防止に直結します。
勤怠管理システムには、シフトと実績の差異を自動で検出する機能が備わっているものが多く、現場の状況に即応できます。
残業が予定外に発生した場合、その場でアラートが表示され、管理者がすぐに対応可能です。
このような機能を活用すれば、無理のない働き方を実現できます。
(3)手作業の勤怠集計をデジタル化する手段
Excelや紙での集計作業には、ミスや手間がつきものです。
勤怠管理システムを活用すれば、出退勤データから自動で労働時間を集計し、残業・休暇管理も一元化できます。
その結果、集計作業にかかっていた時間を大幅に削減できるほか、チェック漏れや計算間違いも防げるようになります。
業務全体の効率を高めたい場合、システムの導入は有効な選択肢です。
(4)管理者の負担を減らす自動化の導入
勤怠管理の煩雑さは、管理者の大きな負担となっています。
シフト作成やアラート通知、打刻ミスの修正通知などを自動化することで、作業量の軽減が可能です。
スタッフの希望をもとにシフト案を自動生成できるシステムであれば、作業時間は半分以下に抑えられる場合もあります。
その分、マネジメントや生産性向上に集中できるようになるでしょう。
4.勤怠管理システムを導入するメリット

製造業で発生しやすい勤怠管理の課題は、手作業による集計ミスや管理者の負担といった、現場全体の効率を下げる要因にもなり得ます。
こうした課題の多くは、勤怠管理システムの導入によって改善が期待できます。
単なる記録の自動化にとどまらず、労務リスクの低減や従業員満足度の向上といった効果も見込めるのがポイントです。
- 法令遵守の強化と対応の効率化
- 労使間トラブルの未然防止
- 管理業務の効率化と人件費削減
- 現場スタッフの働きやすさ向上
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)法令遵守の強化と対応の効率化
労働時間の把握や36協定の遵守は、企業として避けて通れない責任です。
勤怠管理システムには、時間外労働や休憩時間の不足など、違法状態を未然に検出するアラート機能も備わっています。
コンプライアンス体制を強化したい企業にとって、強力なサポートになります。
(2)労使間トラブルの未然防止
「打刻ミスがあった」「残業時間が合っていない」といったトラブルは、従業員との信頼関係に悪影響を及ぼしかねません。
システムによって記録が一元化されれば、曖昧さがなくなり、証拠としても明確になります。
過去のデータもすぐに確認できるため、誤解や揉め事の防止にもつながるでしょう。
結果的に、安心して働ける職場環境づくりに寄与します。
(3)管理業務の効率化と人件費削減
人の手での勤怠集計やシフト作成は、膨大な時間と労力がかかる作業です。
勤怠管理システムを導入すれば、こうした業務の多くを自動化でき、ミスも大幅に削減されます。
集計作業にかかっていた1日分の工数が1時間に短縮されたケースもあります。
管理業務にかかる人件費も抑えることが可能です。
(4)現場スタッフの働きやすさ向上
勤怠管理が整っている職場は、スタッフにとっても安心できる環境です。
スマホでの打刻やシフトの確認、休暇申請のデジタル化により、利便性が大きく向上します。
夜勤明けにその場で勤怠を確認し、すぐに修正依頼を送れるようになれば、ストレスの軽減につながります。
従業員満足度の向上にも効果があるといえるでしょう。
シフト制の職場向け勤怠管理システム「R-Kintai」

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。
徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。
打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。

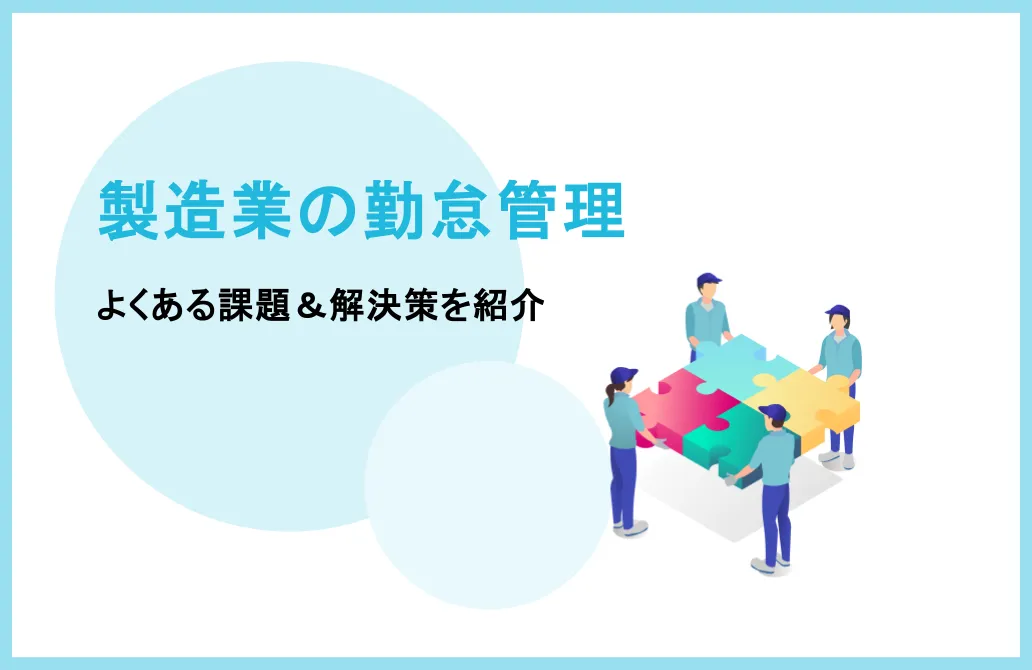
人気記事