「勤怠管理のやり方は、あの人しか知らない」
そんな状態に心当たりがある企業も多いのではないでしょうか。
勤怠管理は日常的な作業である一方、属人化しやすい業務のひとつです。
属人化を放置していると、ミスの発見が遅れたり、引き継ぎが困難になるなど、さまざまなリスクが生じます。
本記事では、勤怠管理業務の属人化を解消するために押さえるべき課題と原因、そして具体的な対策を段階的に解説します。
1.勤怠管理業務が属人化すると起こりうる問題
「この業務はあの人しかわからない」状態は、勤怠管理の現場でよく見られる課題です。
担当者が長年の慣習や個人のやり方で処理しているうちはスムーズに見えるかもしれませんが、その裏では大きなリスクが潜んでいます。
属人化を放置していると、業務の引き継ぎやトラブル対応が困難になり、組織全体の効率や信頼性にも悪影響を及ぼしかねません。
ここでは、勤怠管理業務が属人化することで起こりうる主な問題を3つに整理しました。
- 業務がブラックボックス化する
- ミスやトラブルのリスクが高まる
- 業務効率が悪化し、担当者に負荷が集中する
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)業務がブラックボックス化する
勤怠管理業務が属人化すると、業務の中身がブラックボックス化してしまいます。
担当者以外が手順を知らず、業務の全容が見えにくくなるからです。
休暇申請の処理ルールや残業計算の方法が口頭や感覚的なやり方に頼っていると、担当者が不在になった瞬間に対応不能になるおそれがあります。
こうした状態は、組織全体の透明性や信頼性にも悪影響を与えるでしょう。
(2)ミスやトラブルのリスクが高まる
属人化した勤怠管理は、ミスやトラブルが起きやすい状態をつくります。
担当者一人に処理が集中し、ダブルチェックの仕組みが働かないためです。
給与計算の元になる勤怠データを誤って入力してしまった場合、誰も気づかずにそのまま支給処理が行われる可能性があります。
人為的なエラーを防ぐには、業務の属人化を解消し、複数人で確認できる仕組みが必要です。
(3)業務効率が悪化し、担当者に負荷が集中する
勤怠管理が特定の人にしかできない状況では、担当者に過度な業務負荷がかかります。
マニュアルや共有体制が整っていないと、繁忙期やトラブル発生時に対応しきれなくなるからです。
締め日前に申請や修正対応が集中した際、属人化していると残業や休日出勤で対応するしかないケースも珍しくありません。
これは効率面だけでなく、担当者のモチベーションや離職リスクにも影響を与えるでしょう。
2.なぜ勤怠管理の属人化が起こるのか?主な3つの原因

勤怠管理業務の属人化は、偶然に起こるものではありません。
多くの場合、日々の業務運用のなかに属人化を招きやすい構造や習慣が存在しています。
特定の担当者に頼ったまま運用が続けば、その人がいないだけで業務が止まってしまうリスクも高まるでしょう。
ここでは、勤怠管理が属人化してしまう主な原因を3つの観点から整理しました。
- 紙やExcelによる管理が続いている
- 担当者にノウハウが集中している
- 業務フローやルールが明文化されていない
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)紙やExcelによる管理が続いている
勤怠管理の属人化が起こる大きな要因のひとつは、紙やExcelといった手作業中心の管理方法にあります。
このような方法では、処理や集計の手順が個人のやり方に依存しやすくなり、他の人が把握しにくくなる傾向があります。
たとえば、勤務時間の集計をExcelで担当者が独自に関数やフォーマットを作っていると、急な引き継ぎの際に誰も対応できなくなることがあります。
業務の再現性を高めるには、属人化しやすい管理方法からの脱却が必要です。
(2)担当者にノウハウが集中している
属人化の背景には、勤怠管理に関する知識やノウハウが特定の担当者に集中している状況があります。
長年同じ人が対応していると、手順や判断基準が感覚的になりやすく、マニュアルが整備されないままになりがちです。
たとえば、「このケースはいつもこう処理している」という口頭伝承のような形が続くと、他のメンバーでは正確な対応が難しくなります。
業務を見える化し、誰でも対応できる仕組みに変えることが求められます。
(3)業務フローやルールが明文化されていない
勤怠管理の手順やルールが明文化されていないことも、属人化を招く原因になります。
書面やデジタルで明確に共有されていないと、判断が人によってばらつき、情報の属人化が進んでしまうためです。
遅刻・早退の取り扱いについて明文化されていないと、担当者の裁量で処理が変わることもあります。
組織として一貫性のある対応を行うには、運用ルールを文書化し、共有することが重要です。
3.業務の属人化を解消する具体的な手順4ステップ

属人化は、業務フローの不透明さや担当者への依存、非効率な手段の積み重ねによって起こるものです。
そのため、属人化を解消するには、段階的かつ具体的な対策を講じることが欠かせません。
ここでは、勤怠管理の属人化を解消するための手順を4つのステップに分けて紹介します。
- 現行の業務フローを可視化する
- マニュアルを整備し、業務を標準化する
- 業務を分散させる体制をつくる
- システムを導入し自動化・一元化する
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)現行の業務フローを可視化する
属人化解消の第一歩は、現在の業務がどのように行われているかを見える化することです。
可視化しないままでは、どの部分が個人に依存しているのか判断できず、改善に着手しにくくなります。
「どのタイミングで、どの作業を、どの手順で行っているか」を明文化することで課題が見えてきます。
現状の整理が属人化から脱却する土台となるでしょう。
(2)マニュアルを整備し、業務を標準化する
属人化を防ぐには、誰が見ても同じように対応できるマニュアルの整備が欠かせません。
マニュアルがないと、手順が担当者の記憶や経験に依存し、業務の再現性が低くなります。
たとえば、「有給申請の承認フロー」や「勤怠修正の入力手順」などをドキュメント化し、誰でも確認できる状態にすれば、急な担当交代にも対応できます。
業務の標準化によって、人に頼らない運用が実現します。
(3)業務を分散させる体制をつくる
業務の集中を防ぐには、複数人で業務を担う体制を整えることが有効です。
一人に頼りきりの状況では、不在時に業務がストップするリスクが常に伴います。
たとえば、勤怠の締め処理を2名以上でチェックする、月次報告を交代で作成するといった運用を取り入れれば、業務の偏りを防げます。
属人化を防ぐためには「分担」がキーワードです。
(4)システムを導入し自動化・一元化する
属人化を根本的に解消するには、勤怠管理システムの導入による自動化・一元化が有効です。
アナログな作業や手動での集計は、担当者ごとのやり方に依存しやすく、ミスの温床にもなります。
出退勤の打刻・残業申請・集計がすべてシステム上で完結すれば、誰が対応しても同じ結果が得られるようになります。
ツールの力を借りることで、業務の属人性を大きく減らすことができるでしょう。
4.属人化の解消に勤怠管理システムを導入するメリット

勤怠管理の属人化を防ぐうえで、システムの導入は非常に効果的な手段です。
これまで人の手や経験に頼っていた業務を、仕組みとして標準化・自動化することで、「特定の人にしかできない状態」から脱することができます。
属人化のリスクを減らしながら、業務の効率や正確性も向上させられるのが勤怠管理システムの強みといえるでしょう。
ここでは、勤怠管理システムを導入することで得られる、属人化解消に直結する主なメリットを紹介します。
- 誰でも扱える仕組みになる
- 引き継ぎ・共有がしやすくなる
- ミスの防止・対応スピードの向上につながる
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)誰でも扱える仕組みになる
勤怠管理システムを導入することで、誰でも操作できる環境を整えることが可能です。
Excel操作や紙の台帳管理に比べて、システムは画面上の案内に従うだけで処理ができるため、専門知識が不要になります。
たとえば、新人スタッフでも数分のレクチャーで打刻や申請ができるシステムであれば、「この人にしかできない業務」を減らすことができます。
結果として、担当者が変わっても継続的に同じ水準の業務が保たれるようになります。
(2)引き継ぎ・共有がしやすくなる
勤怠管理システムを導入すると、業務内容がシステム上に集約され、情報の引き継ぎや共有が格段にしやすくなります。
これまで担当者の頭の中だけで管理されていた処理手順や判断基準が、誰でも確認できる形で可視化されるからです。
たとえば、承認履歴や修正対応の記録がシステム上に残っていれば、後任者が過去の対応内容をすぐに把握できます。
業務の継続性が確保され、属人化による混乱を未然に防ぐことができるでしょう。
(3)ミスの防止・対応スピードの向上につながる
システムを活用することで、勤怠管理の正確性が向上し、ミスを抑えることができます。
人手の作業に比べて、システムは一定のルールに基づいて処理を行うため、ミスの温床になりにくい構造です。
たとえば、残業時間の上限を超えた場合に自動でアラートが出る仕組みがあれば、担当者が気づかなくても早期対応が可能になります。
チェックの手間も減り、スピーディな管理が実現する点も大きなメリットです。
5.システム導入なしで属人化を防ぐ方法
勤怠管理の属人化は放置すればするほど、改善に時間と手間がかかるようになります。
しかし、必ずしもシステムを導入しなければ対策できないわけではありません。
日々の業務の中で、ちょっとした工夫や見直しを積み重ねることで、属人化を防ぐ仕組みづくりは十分に可能です。
ここでは、システムを使わなくてもすぐに始められる属人化対策を4つご紹介します。
- 業務マニュアルを作成・更新する
- 複数人で業務を担当する仕組みをつくる
- 業務フローを見える化する
- 業務の棚卸しと見直しを定期的に行う
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)業務マニュアルを作成・更新する
属人化を防ぐ基本は、業務の手順や判断基準を明文化することです。
作業内容が頭の中だけにある状態では、他の人の対応が難しくなります。
「勤怠締めの手順」や「イレギュラー対応の判断ルール」を簡単なマニュアルとして書き起こすだけでも、情報の属人化を減らす効果があります。
身近な作業から整理することで、共有の第一歩を踏み出しましょう。
(2)複数人で業務を担当する仕組みをつくる
一人で全ての勤怠業務を担っている状態は、属人化を深める大きな要因です。
複数人で同じ業務に関わることで、知識の偏りや作業の属人性を軽減できます。
月末処理や承認フローを交代制にする、チェックを2人体制にするなど、分担を意識するだけでも効果的です。
負担の偏りを防ぎ、急な欠員時にも対応できる体制づくりが求められます。
(3)業務フローを見える化する
勤怠管理のどの作業がどのタイミングで、どのように行われているかを明らかにすることも、属人化防止に役立ちます。
業務全体の流れが見えないと、手順や責任の所在が曖昧になりやすいためです。
ホワイトボードや共有ファイルに「週ごとの勤怠処理の流れ」を書き出しておくだけでも、全体の把握がしやすくなります。
可視化によって、他のメンバーが業務に入りやすい環境が整います。
(4)業務の棚卸しと見直しを定期的に行う
属人化を防ぐには、現在の業務のやり方が本当に最適かどうかを見直すことも重要です。
長年同じ人が担当していると、非効率な手順や不要な作業がそのまま続いてしまうケースも少なくありません。
毎月の勤怠報告書を紙でまとめている場合、それが本当に必要かチームで話し合うことが改善の糸口になります。
業務の棚卸しは、全体の業務効率向上にもつながります。
属人化を解消する勤怠管理システム「R-Kintai」

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。
徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。
打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。

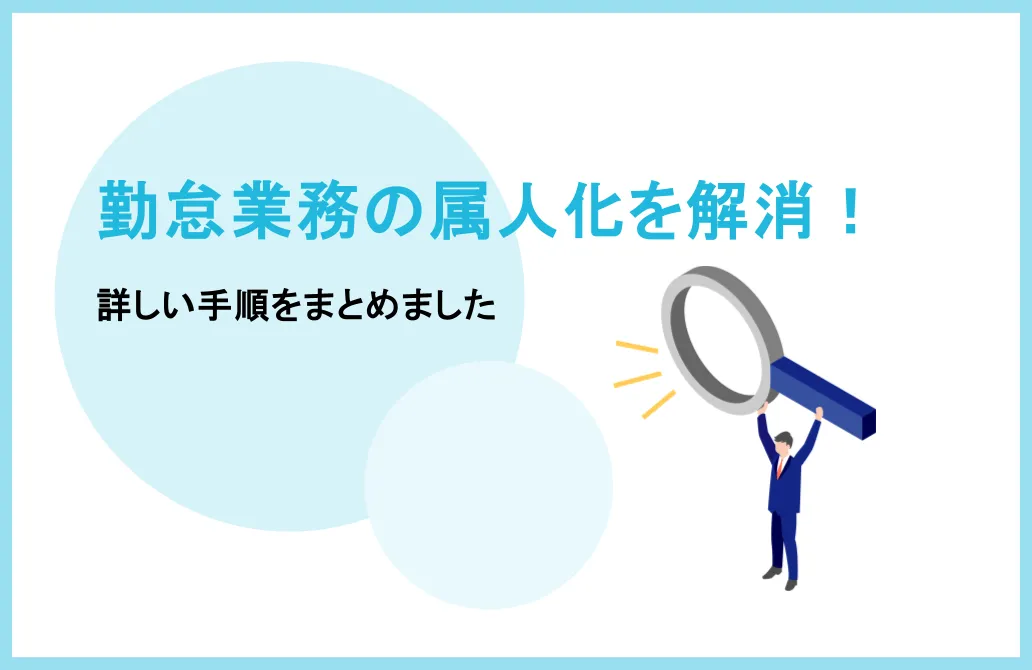


人気記事