宿直勤務は、睡眠や待機を含む特殊な勤務形態ゆえに、勤怠管理が複雑です。
割増賃金の計算、呼び出し対応の扱いなど、通常の勤怠管理では発生しない判断が求められます。
ルールを曖昧にしたまま運用すると、記録のズレや支給漏れが起きやすくなります。
本記事では、宿直勤務の運用上のポイント、宿直に対応できる勤怠管理システムの機能と選び方をまとめました。
宿直特有の課題に向き合いながら、効率的な勤怠管理を実現するヒントとしてお役立てください。
1.宿直勤務とは?夜勤との違い
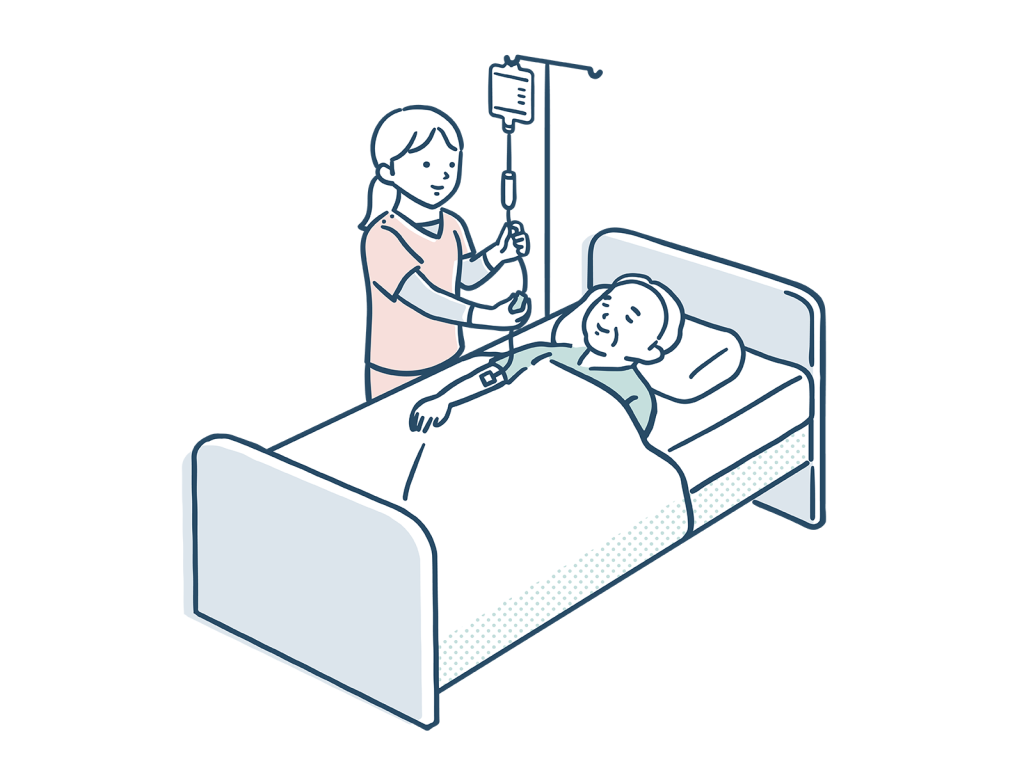
宿直勤務は、介護施設や医療機関、警察、警備会社などで、夜間の施設管理や対応を目的とした働き方です。
通常の夜勤と同じ扱いにしてしまうと、労働時間や割増賃金の計算で誤りが生じることがあります。
労働基準法では「宿直」と「夜勤」を別の概念として定義しているため、企業が適切に区別して運用することが重要です。
ここでは、宿直勤務の基本と夜勤との違いを整理しました。
- 宿直は「睡眠・待機」を含む特殊な勤務形態
- 夜勤は通常の勤務として扱われる
- 宿直は労働基準監督署への届出が必要
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)宿直は「睡眠・待機」を含む特殊な勤務形態
宿直は、業務の中心が「夜間の見回りや待機」であり、一定時間の睡眠を前提とした働き方です。
“労働している時間”の定義が異なり、労働時間の計算方法も一般勤務と異なります。
実態に即した管理を行わないと、働いた時間の把握が曖昧になりやすい面があります。
(2)夜勤は通常の労働時間として扱われる
夜勤は、日中と同じく“通常の業務を夜に行う勤務”として扱われます。
そのため、労働時間・休憩・深夜割増などの扱いは一般勤務と同じ枠組みで管理されます。
睡眠を前提にしない働き方のため、労働時間の把握や割増計算はよりシンプルです。
(3)宿直は労働基準監督署への届出が必要
宿直勤務は、労働基準法上「特別な扱い」とされています。
原則として、労働基準監督署への届出が必要です。
企業が宿直制度を導入する際、法的な基準を満たさずに運用すると、労働時間の扱いが不適切となり、後の是正指導につながるリスクもあります。
2.宿直で発生しやすい勤怠管理の問題

宿直勤務は「睡眠を含む待機」という特徴があるため、通常の夜勤とは異なるトラブルが起きやすい働き方です。
業務量が日によって変わることも多く、勤怠データと実態がずれやすい環境でもあります。
ここでは、宿直で特に問題になりやすい勤怠トラブルを整理しました。
- 睡眠時間と実働時間の境界が曖昧になる
- 宿直手当と割増賃金の扱いを混同しやすい
- 記録方法がバラつきやすい
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)睡眠時間と実働時間の境界が曖昧になる
宿直は「睡眠を含む勤務」であるため、どこまでが休息で、どこからが実働なのかが曖昧になりやすい特徴があります。
申告の仕方が人によって違うと、勤怠データに大きな差が生じます。
境界が不明確なまま運用すると、実際に働いた時間よりも少なく、または多く申告されるケースが発生し、後からの確認作業も煩雑になります。
休息・実働の判断基準を統一し、全員が同じ基準で記録できる状態を整えておくことでズレを防ぎやすくなります。
(2)宿直手当と割増賃金の扱いを混同しやすい
宿直手当は“宿直に対する定額の手当”であり、深夜割増とは別のものですが、この違いを混同してしまう職場も少なくありません。
誤った扱いのままで給与計算を行うと、不足や過剰支給の原因になります。
手当の基準が曖昧なままだと、スタッフからの問い合わせが増え、説明の手間も増えてしまいます。
手当と割増の違いをルールとして共有しておくことでトラブルを避けやすくなります。
(3)記録方法がバラつきやすい
宿直勤務は業務量が一定でないため、対応した内容の記録方法が統一されにくく、結果として申告内容にばらつきが生まれます。
緊急対応の回数や対応時間の記録が曖昧になると、実態が正しく反映されません。
記録が統一されていないと、勤怠管理側が確認する手間が大きくなり、翌月以降の運用にも影響します。
対応内容を記録するフォーマットを用意し、誰でも同じ方法で記録できる体制が必要です。
3.宿直の勤怠管理で押さえておきたい基本ルール

宿直勤務を適切に運用するには、夜勤とは異なる前提に合わせた“基準づくり”が欠かせません。
宿直は睡眠を含む待機を前提とした働き方であるため、実働の扱い・呼び出し対応・手当の支給基準など、通常勤務では起こらない特有の判断ポイントが多く存在します。
宿直を安全かつ適切に管理するために必要な基本ルールを整理しました。
- 宿直として認められる条件を明確にする
- 睡眠・休息と実働の境界を定義する
- 呼び出し対応の扱いを統一する
- 宿直手当の基準と支給ルールを決める
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)宿直として認められる条件を明確にする
宿直勤務は「軽度の業務・待機・睡眠を伴う勤務」です。
一定の条件を満たしていないと宿直として扱えない場合があります。
基準が曖昧なまま運用すると、労働時間として扱うべき部分を見落とす可能性も。
後の是正指導につながるリスクもあります。
宿直の定義や条件を社内で共有し、法令に沿った適切を行いましょう。
(2)睡眠・休息と実働の境界を定義する
宿直では「休息中なのか」「呼び出されて実際に働いているのか」を区別する必要があります。
この境界が曖昧だと、労働時間の計算が一致しない状態になりやすく、勤怠データの整合性が保てません。
判断がバラバラのままでは、スタッフによって記録の仕方が異なり、実態をつかみにくくなります。
境界を定め、全員が同じ基準で記録できる環境を整えることで、時間外の扱いも正確に行えます。
(3)呼び出し対応の扱いを統一する
宿直中の呼び出しは“勤務時間”に含まれるため、その対応時間をどのように記録するかが重要です。
対応が複数回発生する場合、申告内容とのズレが起きやすい傾向があります。
扱いが明確でないと、労働時間に差が出てしまい、給与計算でもトラブルの原因になります。
呼び出しが発生した際の処理手順や申告方法を統一することで、勤怠管理が安定しやすくなります。
(4)宿直手当の基準と支給ルールを決める
宿直手当自体は、“宿直に入ること”に対して支払われる定額の手当です。
実働によって変動するものではありません。
この点を深夜割増と混同してしまうと、給与計算の誤りにつながります。
手当の金額・支給条件・実働が発生した際の扱いをルールとして整理し、明確で公平な運用ができます。
4.宿直に対応できる勤怠管理システムの機能

宿直勤務は、睡眠・待機・緊急対応などが混在するため、手作業での勤怠管理ではミスが起きやすくなります。
労働時間の区分や実働の判断が細かく求められる場面も多く、紙やエクセルでは追跡しきれないケースも少なくありません。
複雑な勤務形態にも対応できる勤怠管理システムを活用すると、宿直特有の判断や計算を自動化でき、運用の負担が大きく軽減されます。
ここでは、宿直に対応できるシステムの主な機能を整理しました。
- 睡眠・休息と実働を区別して記録できる
- 呼び出し対応の実働時間を正確に反映できる
- 宿直手当・深夜割増の自動計算ができる
- 宿直の勤務実績を一覧で把握できる
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)睡眠・休息と実働を区別して記録できる
宿直では「休息中」と「働いている時間」を分けて記録する必要があります。
システムを使うと、区分を切り替えながら記録できるため、正確な管理が可能です。
この区別が曖昧だと、勤怠データの整合性が取りづらくなるでしょう。
記録区分を自動で切り替えたり、ボタン操作で明確にできるシステムを利用すると、実態に沿ったデータが蓄積されます。
(2)呼び出し対応の実働時間を正確に反映できる
宿直中の緊急呼び出しは勤務時間として扱う必要があります。
システムでは、呼び出し対応の開始・終了を簡単に記録でき、時間外労働に自動で計上できます。
紙や口頭での申告では、対応時間の抜けやズレが起こりやすく、後の確認に手間がかかるもの。
正確に反映されることで、勤務実態が明確になり、給与計算の負担も軽減されます。
(3)宿直手当・深夜割増の自動計算ができる
宿直手当は定額支給が一般的ですが、深夜帯の実働が発生した場合は別途割増賃金が必要です。
システムを使うと、宿直手当と深夜割増を別々の基準で自動計算でき、支給漏れや過剰支給のリスクを抑えられます。
自動計算によって計算基準が統一され、適正な支給がしやすい環境が整備できるでしょう。
(4)宿直の勤務実績を一覧で把握できる
宿直は担当者によって対応内容がばらつきやすいため、誰がどのような勤務を行ったのかを一覧で確認できるシステムが役立ちます。
緊急対応の回数や実働時間の偏りも可視化でき、業務量の調整にも活用できます。
実績が個別で管理されている状態では、勤務状況が見えにくく、評価や配置の判断が困難です。
一覧で確認できるシステムなら、運用の公平性も保ちやすくなります。
シフト制の職場にぴったりの勤怠システム「R-Kintai」

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。
徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。
打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。

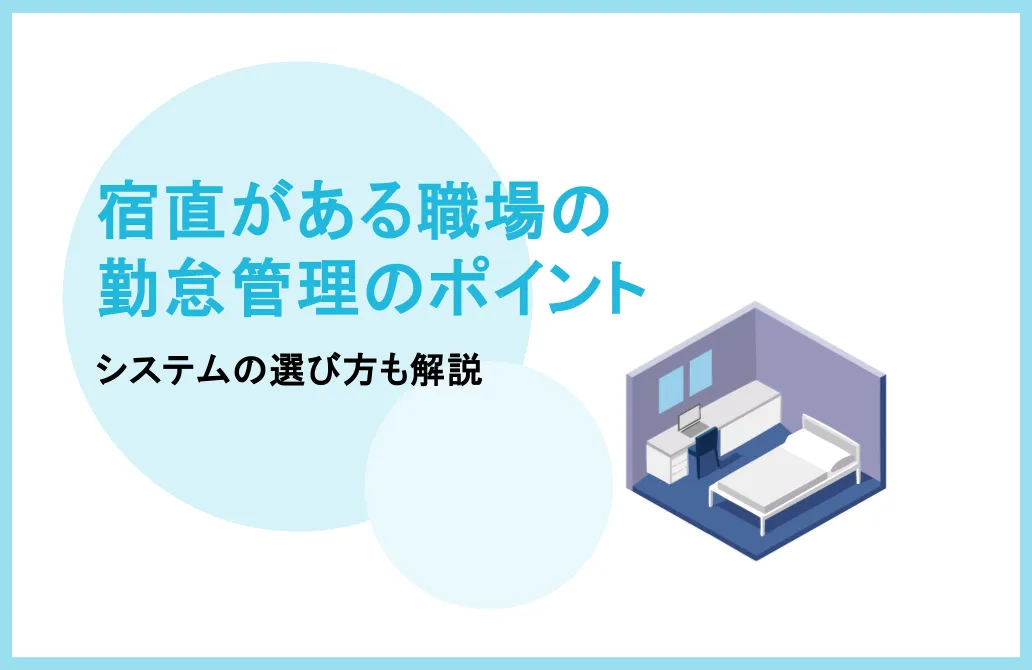
人気記事