直行直帰の働き方は柔軟性が高く、生産性向上にもつながる一方で、勤怠管理の面では注意が必要です。
出退勤の基準、移動時間や休憩の扱いが曖昧になるため、実態を把握しにくい場面が出てきます。
申請内容と実働の食い違いが積み重なり、給与計算にも影響することも。
本記事では、直行直帰の勤怠管理で起こりやすい疑問やトラブルを紹介しつつ、スムーズに管理するためのコツをまとめました。
現場と管理側の双方がストレスなく働ける環境づくりの参考としてお役立てください。
1.直行直帰の勤怠管理が難しい理由

直行直帰の働き方は、移動が多い業務にはとても便利ですが、勤怠管理の注意点も少なくありません。
出退勤のタイミングが固定されないぶん、実働時間を把握しづらく、申請内容と実態がずれることもあります。
企業としても、明確なルールを決めておかないと運用が不安定になりやすいもの。
ここでは、直行直帰の勤怠管理が複雑になりやすい理由を整理しました。
- 出退勤の判断基準が曖昧になりやすい
- 移動時間の扱いに差が出やすい
- 打刻方法を統一しないと記録がバラつく
- トラブル時の証跡が残りにくい
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)出退勤の判断基準が曖昧になりやすい
直行直帰では、どのタイミングを「出勤」とみなすのかが判断しづらいもの。
朝一の訪問先なのか、その前の準備時間なのかが曖昧になり、申請内容にばらつきが出ます。
判断基準が不統一のまま運用すると、労働時間の整合性が取りづらくなります。
出勤・退勤の基準を明文化し、誰が見ても同じ判断ができるよう整備が必要です。
(2)移動時間の扱いに差が出やすい
訪問先への移動が発生する業務では、「どこまでが勤務時間に含まれるのか」がわかりにくい場面があります。
人によって申請の仕方が違うと、同じ働き方でも労働時間に差が生じて、不公平感も生まれるでしょう。
移動時間が曖昧なままでは、残業の発生状況や勤務実態を正確に把握できません。
業務として扱う移動の範囲を決めておくことで、申請のばらつきを抑え、労働時間を正確に計算しやすくなります。
(3)打刻方法を統一しないと記録がバラつく
直行直帰は、出勤と退勤の場所が毎回異なるため、職場のタイムレコーダーが使えないケースがほとんどです。
スタッフによって記録方法が違うと、管理側が確認する手間が増え、誤りも拾いにくくなります。
記録がばらつく状態だと、勤務実績とシフトの整合性がとれません。
後から修正が必要になる場面が増加します。
スマホ打刻や位置情報付き打刻など、方法を統一することが重要です。
(4)トラブル時の証跡が残りにくい
外出先で働く直行直帰の業務では、作業開始・終了の証跡が残りづらいのが欠点です。
申請内容と実態に差が出たときに確認が難しくなります。
証跡が不十分だと、勤怠修正に時間がかかる上、トラブルの原因が特定しにくく、管理が後手に回りがちです。
訪問ログや位置情報など、第三者が確認できるデータを残す仕組みを整えると、こうしたリスクを減らせます。
2.直行直帰で起こりやすい勤怠トラブル

直行直帰の働き方は、働く場所や状況が日によって異なります。
想定しづらいトラブルが発生することも。
特に、現場判断で動くケースが多い職種では、勤務実態を把握しづらく、申請内容との“ズレ”が積み重なりやすい傾向があります。
ここでは、現場運用のリアルで起きやすいミスや誤解に焦点を当てて整理しました。
- 現場作業の延長で勤務が“自然に伸びる”
- 実働時間が曖昧になる
- “打刻できない時間帯”が発生する
- 緊急対応が勤務扱いかどうか判断しづらい
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)現場作業の延長で勤務が“自然に伸びる”
直行直帰の職場では、訪問先で予想外の対応が発生し、勤務が伸びる場面があります。
本人の申告とシフト上の想定が一致しないと、後からの確認が困難に。
残業申請の漏れや計算ズレが起こりやすくなり、給与計算にも影響します。
報告方法や連絡ルールを整えることで、“自然に増える勤務時間”の食い違いを減らせます。
(2)実働時間が曖昧になる
直行直帰では、顧客対応やトラブル処理で予定外の場所に立ち寄るケースがあります。
このとき、どこからどこまでが勤務扱いか判断が難しく、申告内容にばらつきが生まれがちです。
訪問順や滞在時間が想定していた流れと異なると、勤怠の整合性が取りづらくなります。
立ち寄りが発生した場合の申告ルールを明確にする必要があります。
(3)“打刻できない時間帯”が発生する
外出先では、地下・工場エリア・屋外など、電波が安定しない場所が少なくありません。
打刻が使えない場面があると、正確な時刻が記録できません。
申告内容と実際の勤務がずれやすくなり、管理側の確認負担も大きくなります。
電波状況を考慮した運用ルールを用意すると、トラブルを抑えられます。
(4)緊急対応が勤務扱いかどうか判断しづらい
直行直帰の職場では、移動中に顧客からの連絡が入り、そのまま緊急対応に切り替わることがあります。
この場合、どの時点から勤務として扱うべきかが曖昧になりやすく、スタッフ側と管理側の認識に差が生じることも。
判断基準が揃っていないと、申請のばらつきや労働時間の計算違いにつながります。
緊急対応が発生した際の扱いを明確にし、報告フローを整えておく必要があります。
3.押さえておきたい直行直帰の勤怠管理ルール

直行直帰を適切に管理するには、“明確なルールづくり”が欠かせません。
訪問順や移動時間、緊急対応など、日によって業務の流れが変わるため、判断基準を統一しないと勤怠データのばらつきが発生します。
ここでは、直行直帰の働き方でも安定した勤怠管理ができるように、最低限整えておきたいルールをまとめました。
- 出勤・退勤の定義を明確にする
- 業務として扱う移動の範囲を定める
- 休憩時間の取り方と申告方法を統一する
- 緊急対応が発生した際の扱いを決めておく
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)出勤・退勤の定義を明確にする
直行直帰では、勤務の開始地点や終了地点が毎回異なるもの。
どのタイミングを出勤扱いにするかを統一しておく必要があります。
曖昧な状態だとスタッフによって解釈が分かれ、勤怠データに差が出やすくなります。
訪問先への移動前を出勤とするのか、現地到着時を基準にするのか明文化し、運用のばらつきを抑えましょう。
(2)業務として扱う移動の範囲を定める
直行直帰では移動が多く、移動が勤務に含まれるのか明確にしないと申請にばらつきが出ます。
業務目的の移動と私用の移動を混在させないルールを決めておけば、公平な勤怠管理が可能です。
移動時間の扱いが定まらないまま運用すると、労働時間が増えすぎたり逆に少なくなったりして、給与計算の整合性が取りづらくなります。
「訪問先間の移動は勤務扱い」「自宅から最初の訪問先までの移動は○○扱い」など、基準をはっきりさせておくことで、誤解を防ぎやすくなります。
(3)休憩時間の取り方と申告方法を統一する
現場や状況によって休憩を取るタイミングは変わります。
休憩の扱いを統一しておかないと実働時間が正確に把握できません。
休憩の取り方を個人に委ねると、労働基準法上の休憩取得も確認しにくく、企業側のリスクが増えます。
休憩の定義と申告方法を統一し、最低限守るべきルールを決めておきましょう。
(4)緊急対応が発生した際の扱いを決めておく
直行直帰の業務では、移動中や作業中に急な呼び出しが入る場面があります。
この対応時間をどう扱うかが曖昧なままだと、労働時間の集計に差が生じやすくなります。
緊急対応は発生するタイミングが読めないため、スタッフの判断で申告すると認識のズレが起きやすくなります。
扱いを決めておけば、勤務実態の把握がしやすくなり、修正の手間も減るでしょう。
4.直行直帰の勤怠管理で気をつけたいポイント

直行直帰の勤怠管理は、ルールを整えるだけでは運用が安定しません。
記録のタイムラグや、状況に応じた判断が必要になる場面が多くあります。
日常の運用フローやスタッフとのコミュニケーションにも工夫が必要です。
実務のなかで“特に注意しておきたいポイント”を整理しました。
- 記録タイミングのズレを最小限にする
- 業務連絡の方法を一本化する
- 申請・承認の流れを明確にする
- スタッフの負担を減らす仕組みを整える
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)記録タイミングのズレを最小限にする
直行直帰では、現場の状況で打刻が遅れやすく、申告時間と実働時間の差が生じがちです。
記録のタイミングが定まらない状態だと修正が増え、精度も安定しません。
スマホ通知の設定や、記録タイミングを固定する運用にすると、記録のブレが少なくなり、管理がスムーズになります。
(2)業務連絡の方法を一本化する
直行直帰の働き方では、電話・LINE・メールなど連絡手段の統一が不可欠です。
訪問順の変更や業務延長などが複数ルートで届くと、勤怠の確認にも影響します。
共有ツールやチャットを一本化することで、情報が集まりやすくなり、勤怠の確認もしやすくなります。
(3)申請・承認の流れを明確にする
直行直帰は勤務状況が見えにくく、残業や業務延長の申請があいまいになりがちです。
どの段階で申請し、誰が承認するのかが明確でないと、トラブルの原因になります。
承認フローを明文化し、申請がスムーズに通る仕組みを整えることが負担軽減のカギです。
(4)スタッフの負担を減らす仕組みを整える
直行直帰で働くスタッフは、現場対応に集中しながら勤怠記録を行う必要があります。
記録の手間や負担が大きいと、記録漏れや申請忘れが繰り返される原因になります。
操作が簡単な打刻方法や自動化できる仕組みを採用し、正確な運用を実現しましょう。
多様な働き方に対応する勤怠システム「R-Kintai」

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。
徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。
打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。

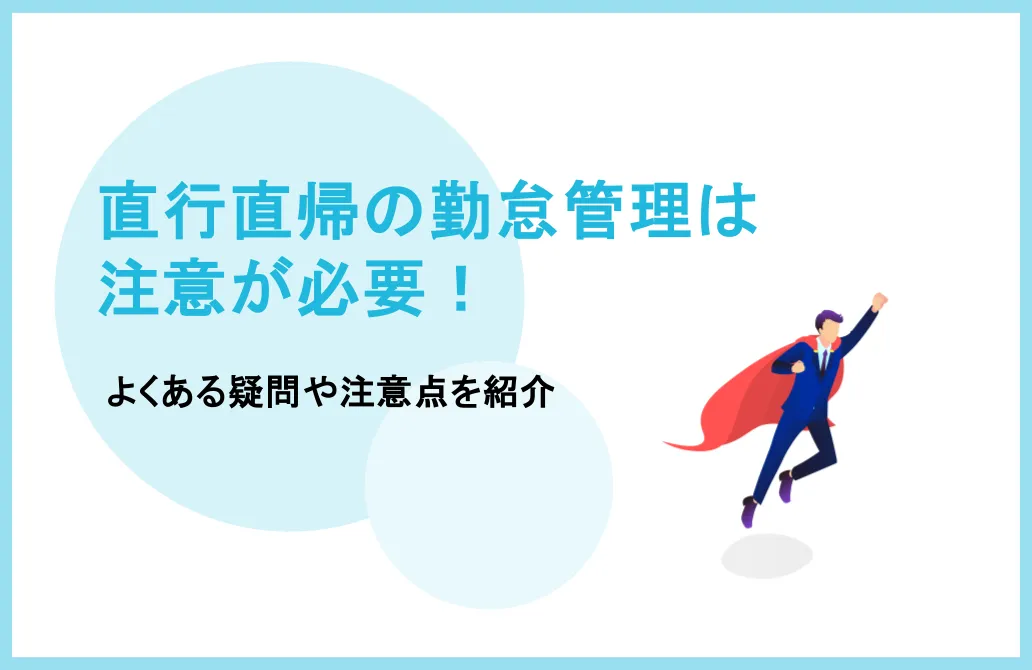
人気記事