労働時間の管理は、企業と労働者どちらにとっても極めて重要です。
中でも「月平均所定労働時間」という概念は、労働時間の適正な設定や残業代の計算に影響を与えます。
本記事では、「月平均所定労働時間」の定義から計算方法、重要性について詳しく解説します。
労働基準法に基づく労働時間の管理方法や割増賃金についても紹介しますので、参考にしてください。
1.月平均所定労働時間とは
「月所定労働時間」とは、労働者や企業ごとに定められた「従業員が勤務する時間(労働時間)」を指す用語です。
就業規則や雇用契約書に記載されている、始業時間から終業時間までのうち、休憩時間を引いたものが所定労働時間にあたります。
月平均所定労働時間とは、「1か月当たりの平均の所定労働時間」のこと。
法定外残業、深夜労働、法定休日労働の割増賃金を計算する際に用いられます。
各月のばらつきをなくすために、月平均で計算します。
2.月平均所定労働時間の計算方法
月平均所定労働時間は、以下の計算式から求められます。
月平均所定労働時間=年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12ヵ月
年間所定労働日数は「365日-1年の休日合計日数」で求めることができます。
また、1日の所定労働時間は「始業時間〜終業時間までのうち、休憩時間を引いたもの」のことです。
(例)
年間休日120日、1日の所定労働時間8時間の企業の場合
(365日-120日)×8時間÷12か月
=245日×8時間÷12か月
=163.3
月平均所定労働時間は163.3時間となります。
ちなみに、労働基準法では月平均所定労働時間の上限を173.8時間と定めています。
これを超えている雇用契約は法律違反となるため注意しましょう。
3.月平均所定労働時間はなぜ重要なのか
月平均所定労働時間が重要な理由は、残業代の計算に直接影響を及ぼすからです。
労働基準法では、法定労働時間を超える労働に対して割増賃金(残業代)を支払うことが義務付けられています。
労働基準法で定められている労働時間や休日、残業時間と照らし合わせながら見ていきましょう。
法定労働時間の基準設定
労働基準法第32条では、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間を超えてはならないと定められています。
これを基にして、月平均所定労働時間が設定されます。
残業代の計算との関わり
残業には「法定内残業」「法定外残業」の2種類が存在します。
法定内残業は、所定労働時間を超えるものの、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えない分の残業を指します。
法定外残業は、これを超える残業のことです。
例えば、所定労働時間が7時間(8時始業・16時終業)の会社で、8時から18時(休憩60分)まで働いた場合、2時間の残業のうち16~17時は法定内残業、17~18時は法定外残業に当たります。
法定内残業は割増賃金不要ですが、法定外残業には割増賃金が発生します。
この割増率は深夜労働(22時から翌5時までの労働)や休日労働の場合にはさらに高くなることがあります。
割増賃金の制度は、残業を促進するものではなく、むしろ労働者を過度な労働から守り、適切な報酬を保証するためのものです。
状況別の割増率を以下の表にまとめましたので参考にしてください。
| 残業の種類 | 割増率 |
| 法定外労働時間(時間外労働) | 25% |
| 1ヶ月60時間超の時間外労働 | 50% |
| 深夜労働(22~5時) | 25% |
| 時間外労働かつ深夜労働 | 50% |
| 1ヶ月60時間超の時間外労働かつ深夜 | 75% |
| 法定休日労働 | 35% |
| 法定休日労働かつ深夜 | 60% |
4.あわせておさえたい!労働時間と休憩時間の関係
労働基準法では、労働者の健康と安全を守るために、労働時間に応じた休憩時間が定められています。
労働者が一定の時間働いた場合に必ず休憩を取る権利が保障されており、企業は適切に休憩時間を設定する必要があります。
労働基準法で定められた休憩時間
①労働時間が6時間を超える場合
6時間を超えて8時間以下の労働時間に対しては、少なくとも 45分 の休憩を与えなければなりません。
例:午前9時から午後3時30分までの6時間30分働く場合、45分の休憩が必要です。
②労働時間が8時間を超える場合
8時間を超える労働時間に対しては、少なくとも 1時間 の休憩を与えなければなりません。例:午前9時から午後6時までの9時間働く場合、1時間の休憩が必要です。
休憩時間の基本ルール
休憩時間には「一斉に付与する」「労働時間の途中に付与する」「自由にできる」という3つの原則があります。
①一斉に付与する
休憩時間は基本的に全ての労働者に一斉に与えられるべきです。ただし、労働者の意見を聞いたうえで、労働基準監督署長の許可を得れば、交替で与えることも認められます。
②労働時間の途中に付与する
休憩時間は労働時間の最初や最後ではなく、途中に付与するものと決められています。
例えば、9時から18時までが労働時間の場合、1時間の休憩が必要ですが「17時から18時を休憩時間にする」といったことは認められていません。
③自由にできる
休憩時間は労働者が自由に利用できる必要があります。
労働者が自由に過ごすことができない場合、適切な休憩とはみなされません。
休憩時間の例外と特例
休憩時間は「交代制勤務」の場合や「特定の業種」については、例外的な扱いが認められています。
①交替制勤務の場合
交替制勤務など特定の状況では、一斉に休憩を取ることが困難な場合があります。このような場合には、例外的に個別に休憩を取ることが認められることがあります。
②特定の業種の場合
一部の業種(例:運輸業、医療業など)では、特別な事情により休憩時間の取り方が異なる場合があります。
この場合でも、労働者の健康と安全を守るための配慮が必要です。
働く人に寄り添う勤怠管理システム「R-Kintai」

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。
徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。
打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。

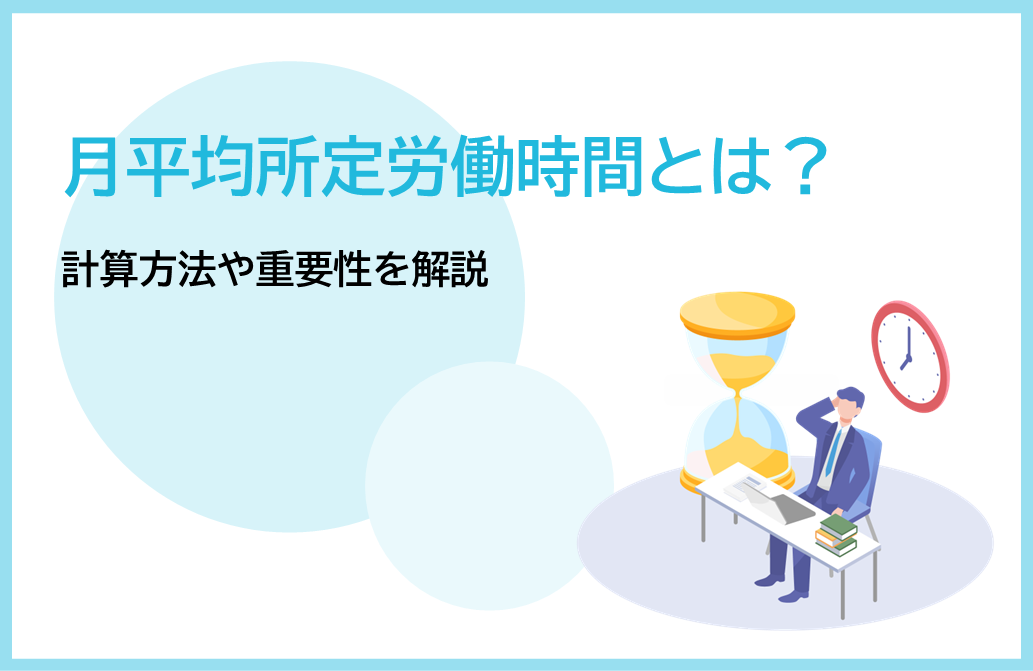
人気記事